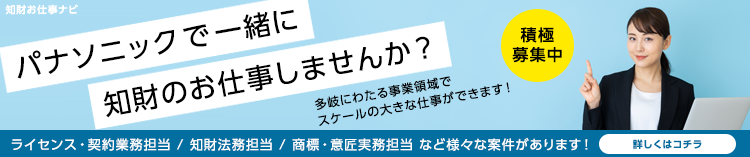| 娭楢怰寛 |
怰敾1968-317 怰敾1970-9403 怰敾1957-106 |
|---|
偙偺敾椺偵偼丄壓婰偺敾椺丒怰寛偑娭楢偟偰偄傞偲巚傢傟傑偡丅
| 怰敾斣崋乮帠審斣崋乯 | 僨乕僞儀乕僗 | 尃棙 |
|---|---|---|
| 敾椺 | 幚梡怴埬 | |
| 徍榓53峴僂29 | 敾椺 | 幚梡怴埬 |
| 暯惉19峴働10300怰寛庢徚惪媮帠審 | 敾椺 | 摿嫋 |
| 暯惉17儚2649摿嫋尃怤奞嵎巭摍惪媮帠審 | 敾椺 | 摿嫋 |
| 暯惉20峴働10151怰寛庢徚惪媮帠審 | 敾椺 | 摿嫋 |
| 娭楢儚乕僪 | 峫埬 / 恾柺 / 峔憿 / 曗惓 / 愝掕搊榐 / 尭弅 / 嶍彍 / 幚巤椺 / 柧嵶彂 / 惪媮偺斖埻 / 柧椖偱側偄婰嵹 / |
|---|
| 尦杮PDF |
嵸敾強廂榐偺慡暥PDF傪尒傞
|
|---|---|
| 尦杮PDF |
嵸敾強廂榐偺暿巻1PDF傪尒傞
|
| 帠審 |
徍榓
55擭
(峴働)
136崋
|
|---|---|
| 嵸敾強偺僨乕僞偑懚嵼偟傑偣傫丅 | |
| 嵸敾強 | 搶嫗崅摍嵸敾強 |
| 敾寛尵搉擔 | 1981/11/05 |
| 尃棙庬暿 | 幚梡怴埬尃 |
| 慽徸椶宆 | 峴惌慽徸 |
| 庡暥 |
尨崘偺惪媮傪婞媝偡傞丅 慽徸偺憤旓梡偼丄尨崘偺晧扴偲偡傞丅 |
| 帠幚媦傃棟桼 | |
|---|---|
|
摉帠幰偺媮傔偨嵸敾
堦 尨崘 乽摿嫋挕偑徍榓巐敧擭敧寧擇嶰擔丄摨挕徍榓巐屲擭怰敾戞嬨巐乑嶰崋帠審偵偮偄偰偟偨怰寛傪庢徚偡丅慽徸偺憤旓梡偼丄旐崘偺晧扴偲偡傞丅乿偲偺敾寛擇 旐崘(杮埬慜偺怽棫偰)乽杮審慽傪媝壓偡傞丅慽徸偺憤旓梡偼丄尨崘偺晧扴偲偡傞丅乿偲偺敾寛(杮埬偵偮偄偰) 庡暥摨巪偺敾寛 |
|
|
摉帠幰偺庡挘
堦 惪媮偺尨場1 摿嫋挕偵偍偗傞庤懕偺宱堒 尨崘偼丄柤徧傪乽峩阆婡偵楢寢偡傞僩儗儔乕偺嬱摦憰抲乿偲偡傞搊榐戞幍嶰堦嬨幍堦崋幚梡怴埬(徍榓嶰榋擭巐寧堦嶰擔弌婅丄徍榓嶰嬨擭擇寧堦幍擔搊榐)偺幚梡怴埬尃幰偱偁傞偑丄徍榓巐屲擭嬨寧堦榋擔丄塃幚梡怴埬偺婅彂偵揧晅偟偨柧嵶彂傪暿巻掶惓栚榐偺偲偍傝掶惓偡傞偙偲偵偮偄偰怰敾傪惪媮偟丄徍榓巐屲擭戞嬨巐乑嶰崋帠審偲偟偰怰棟偝傟偨寢壥丄徍榓巐敧擭敧寧擇嶰擔丄乽杮審怰敾偺惪媮偼惉傝棫偨側偄丅乿巪偺怰寛偑偁傝丄偦偺摚杮偼丄摨擭堦堦寧堦擔尨崘偵憲払偝傟偨丅 2 杮審峫埬偺梫巪(掶惓怰敾惪媮慜偺傕偺) 乽杮暥偵婰偟恾柺偵帵偡傛偆偵峩阆婡儈僣僔儓儞偺堦晹傛傝摦椡傪庢弌偟壦戜3偺屻曽偵墑挿揱摦偡傋偔側偟堦曽僩儗儔乕懁偼儕儎乕僔儎僼僩傛傝壦戜8慜曽偺僸僣僠嬥嬶12晬嬤偵帄傞揱摦憰抲傪愝偗偰丄偦偺憃曽偺摦椡寢崌揰17傪峩阆婡偲僩儗儔乕傪寢崌偡傞寢崌僺儞13幉怱慄忋C乗C偵愝偗偨峩阆婡偵楢寢偡傞僩儗儔乕偺嬱摦憰抲丅乿(暿巻恾柺嶲徠丅)3 怰寛偺棟桼偺梫巪(堦) 杮審怰敾惪媮偺梫巪偼丄搊榐戞幍堦嶰嬨幍堦崋幚梡怴埬偺柧嵶彂傪暿巻掶惓栚榐婰嵹偺偲偍傝掶惓偡傞偙偲傪媮傔傞傕偺偱偁傞丅 (擇) 敾抐 掶惓慜偺幚梡怴埬搊榐惪媮偺斖埻偵婰嵹偟偰偁傞乽憃曽偺摦椡寢崌揰17傪峩阆婡偲僩儗儔乕傪寢崌偡傞寢崌僺儞3幉怱慄忋C乗C偵愝偗偨乿偲偄偆峫埬偺峔惉梫審偵偮偄偰偺幚巤椺偼丄恾柺偲掶惓慜偺柧嵶彂偺婰嵹偐傜傒偰丄乽峩阆婡A偲僩儗儔乕B偺憃曽偺揱摦憰抲偵楢摦偡傞嶱帟幵傪忋壓椉抂偵桳偡傞悅捈揱摦幉偺拞娫偵夘嵼偝偣偨暘棧姎崌帺嵼偺寢崌巕傛傝側傞摦椡寢崌揰17傪丄峩阆婡A偲僩儗儔B傪嵍塃孅愜帺嵼偵寢崌偡傞敳偒憓偟帺嵼偺悅捈寢崌僺儞13幉怱慄C乗C忋偵愝偗丄偙偺偙偲偵傛偮偰丄峩阆婡偲僩儗儔乕偑嵍塃偵孅愜偡傞偲偒偺拞怱偲側傞幉怱慄偲丄峩栒婡偲僩儗儔乕傪寢崌偡傞寢崌僺儞13幉怱慄C乗C偲丄摦椡寢崌揰17傪捠傞悅捈揱摦幉偺幉怱慄偲偺嶰偮偺幉怱慄傪堦抳偝偣偨乿峔憿傪旛偊偰偄傞傕偺偲擣傔傜傟傞丅 師偵丄掶惓慜偺幚梡怴埬搊榐惪媮偺斖埻偵婰嵹偝傟偨峫埬偺峔惉梫審偲丄偙傟偵偮偄偰偺幚巤椺偺峔憿偐傜傒偰丄杮審搊榐幚梡怴埬偺掶惓慜偺峫埬偺梫巪偵偼丄師偺(a)(b)偺擇揰偑尷掕偟偰側偔丄(c)(d)偺擇揰偑柧椖偱側偄傕偺偲擣傔傜傟傞丅 (a) 寢崌僺儞13偑敳偒憓偟帺嵼偱偁傞偺偐斲偐丅 (b) 摦椡寢崌揰17偑暘棧姎崌帺嵼偱偁傞偺偐斲偐丅 (c) 寢崌僺儞13偵傛偮偰寢崌偝傟偰偄傞峩阆婡偲僩儗儔乕偑偳偺晹暘偵偍偄偰嵍塃偵孅愜偡傞偺偐丅 (d) 摦椡寢崌揰17偑愝偗傜傟偰偄傞摦椡寢崌晹偺嬶懱揑側峔憿丅 師偵丄掶惓屻偺幚梡怴埬搊榐惪媮偺斖埻偵婰嵹偝傟偰偄傞乽偦偺憃曽偺摦椡傪寢崌偡傞慁夞帺嵼偺摦椡姎崌寢崌晹傪側偡忋壓偵嶱帟幵傪桳偡傞悅捈揱摦幉17傪峩阆婡偲僩儗儔乕傪嵍塃孅愙帺嵼偵寢崌偡傞寢崌幉怱慄C乗C忋偵愝偗偨乿傪掶惓慜偺乽憃曽偺摦椡寢崌揰17傪峩阆婡偲僩儗儔乕傪寢崌偡傞寢崌僺儞13幉怱慄忋C乗C偵愝偗偨乿偲懳斾偡傞偲丄掶惓慜偵偍偄偰丄峩阆婡偲僩儗儔乕偑嵍塃偵孅愜偡傞偲偒偺拞怱偲側傞幉怱慄偲丄峩阆婡偲僩儗儔乕傪寢崌偡傞寢崌僺儞13幉怱慄C乗C偲丄摦椡寢崌揰17傪捠傞悅捈揱摦幉偺幉怱慄偲偺嶰偮偺幉怱慄傪堦抳偝偣傞偨傔偵昁梫偱偁偮偨乽摦椡寢崌揰乿乽僺儞13乿媦傃乽摦椡寢崌揰17傪寢崌僺儞幉怱慄忋偵愝偗偨乿偑掶惓偺寢壥枙徚偝傟偨偙偲偵挜偟偰丄杮審搊榐幚梡怴埬偺掶惓屻偺峫埬偺梫巪偵偼丄慜婰偟偨嶰偮偺幉怱慄偑堦抳偟側偄傕偺丄偡側傢偪乽寢崌僺儞傛偮偰峩阆婡偲僩儗儔乕傪嵍塃偵孅愜偟側偄傛偆偵寢崌偡傞偲偲傕偵丄忋壓椉抂偵嶱帟幵傪桳偟丄拞娫偵摦椡寢崌揰傪旛偊偰偄側偄悅捈揱摦幉偺幉怱慄傪拞怱偲偟偰峩阆婡偲僩儗儔乕偑嵍塃偵孅愜偡傞傛偆偵峔惉偟偨峩阆婡偵楢寢偡傞僩儗儔乕偺嬱摦憰抲乿偑幚巤椺偲偟偰曪娷偝傟傞偙偲偵側傞偙偲偑柧傜偐偱偁傞丅 偟偐偟側偑傜丄偐偐傞幚巤椺偼丄恾柺偲掶惓慜偺柧嵶彂偵偼側偵傕婰嵹偝傟偰偄側偄偲偙傠偱偁傞偺偱丄暿巻掶惓栚榐宖婰偺(7)媦傃(8)偵傛傞幚梡怴埬搊榐惪媮偺斖埻偺掶惓偼丄幚幙忋幚梡怴埬搊榐惪媮偺斖埻傪曄峏偡傞傕偺偲擣傔傞丅 偟偨偑偮偰丄杮審偺掶惓偼幚梡怴埬朄戞39忦戞2崁偺婯掕偵堘斀偟偰偄傞傕偺偱偁傞丅 4 杮埬慜偺庡挘偵懳偡傞尨崘偺斀榑 旐崘偼丄杮審幚梡怴埬偺搊榐傪柍岠偲偡傞巪偺怰寛(徍榓巐嶰擭怰敾戞嶰堦幍崋)偑妋掕偟偨偙偲(徍榓屲屲擭屲寧堦擔偺忋崘婞媝偺敾寛偵傛偮偰摨柍岠怰寛偑妋掕偟偨偙偲偼擣傔傞丅)偵傛偮偰杮審掶惓怰敾偼慿媦揑偵偦偺懳徾傪幐偮偨偙偲偵側傝丄偟偨偑偮偰丄杮審慽徸偼慽偺棙塿偑懚偟側偄偙偲偵側偮偨巪庡挘偡傞偑丄 幚梡怴埬朄戞39忦戞4崁偵偼乽戞堦崁偺怰敾偼丄幚梡怴埬尃偺徚柵屻偵偍偄偰傕丄惪媮偡傞偙偲偑偱偒傞丅偨偩偟丄戞37忦戞1崁偺怰敾偵傛傝柍岠偵偝傟偨屻偼丄偙偺尷傝偱側偄丅乿偲婯掕偝傟偰偍傝丄偦偺杮暥偐傜偟偰傕掶惓偺懳徾傪幐偮偨偲偒偵傕掶惓偺怰敾惪媮傪偡傞偙偲偑偱偒傞偙偲偼偄偆傑偱傕側偄丅偟偨偑偮偰丄掶惓偺懳徾傪幐偮偨偙偲傪棟桼偲偡傞旐崘偺庡挘偼棟桼偑側偄丅栤戣偲側傞偺偼塃戞39忦戞4崁偨偩偟彂偑柍岠怰敾偵傛傝乽柍岠偵偝傟偨屻偼丄偙偺尷傝偱側偄丅乿偲偟偨婯掕偺堄枴偱偁傞偑丄埲壓弎傋傞偲偍傝塃偨偩偟彂偼丄掶惓偺懳徾偱偁傞幚梡怴埬偺搊榐偵偮偄偰偺柍岠怰寛偑妋掕偟偨偲偒偼丄塃妋掕埲屻怴偨側掶惓怰敾惪媮偑側偟偊側偄偙偲傪婯掕偟偨傕偺偲夝偡傋偒偱偁傝丄杮審偵偍偗傞偛偲偔婛偵學懏拞偺乽掶惓怰敾偺惪媮偼惉傝棫偨側偄丅乿巪偺怰寛偵懳偡傞庢徚惪媮慽徸傪傕晄揔朄偲偡傞庯巪偺婯掕偲夝偡傞偙偲偼偱偒側偄丅偡側傢偪丄 (堦) 掶惓怰敾偼丄柍岠怰敾惪媮偺懳峈庤抜偲偟偰惪媮偝傟傞傕偺偲偟偰傕丄帪娫揑偵偼柍岠怰敾惪媮偺偁傞慜偱偁傞偙偲傕丄摨帪偱偁傞偙偲傕偁傝丄偁傞偄偼柍岠怰敾惪媮偑側偝傟偨屻偱偁傞偙偲傕偁傞丅偙偺傛偆偵偟偰掶惓怰敾偲柍岠怰敾偑尰偵學懏偟偰偄傞応崌偵偼丄掶惓怰敾偺怰寛偵傛偮偰柍岠怰寛偑暍偊傞偙偲偵偨傞偵傕偐偐傢傜偢丄昁偢偟傕掶惓怰敾偺怰寛妋掕屻偱側偗傟偽柍岠怰敾偵偮偒怰棟偡傞偙偲偑偱偒側偄傕偺偲偼偝傟偰偍傜偢丄偁偔傑偱傕摿嫋挕傗嵸敾強偺嵸検偵傑偐偝傟偰偄傞偺偱偁傞(嵟敾徍巐敧丒榋丒堦屲庢徚廤巐敧擭戞嬨暸嶲徠)丅偦偆偡傞偲丄掶惓怰敾惪媮帠審偺學懏拞偵柍岠怰寛偑愭偵妋掕偡傞偙偲偑偁傝偆傞偑丄偙偺応崌丄揔朄側掶惓怰敾偺惪媮傪偟偰偄偨偵傕偐偐傢傜偢丄柍岠怰寛偑愭偵妋掕偡傞偙偲偵傛偮偰掶惓怰敾偵偮偄偰嵸敾傪庴偗傞尃棙偑扗傢傟傞偙偲偵側傞応崌傕婲傝偆傞偑丄偐偐傞帠懺偺惗偢傞偙偲傪慜採偲偡傞夝庍偼摓掙嵦梡偡傞偙偲偑偱偒側偄丅 (擇) 傑偨丄幚梡怴埬朄掜42忦偼丄妋掕怰寛偵懳偡傞嵞怰偺惪媮傪擣傔丄柉帠慽徸朄戞420忦戞1崁媦傃戞擇崁暲傃偵戞421忦(嵞怰偺棟桼)偺婯掕傪弨梡偟偰偍傝丄摨朄戞420忦戞1崁戞8崋偵偼嵞怰帠桼偺堦偮偲偟偰乽敾寛僲婎慴僩堊傝僞儖乧乧峴惌張暘僇屻僲乧乧峴惌張暘僯埶儕僥曄峏僙儔儗僞儖僩僉乿偲偺婯掕傪偍偄偰偄傞丅 偦偆偡傞偲丄柍岠怰寛偺妋掕屻偵丄學懏拞偺掶惓怰敾偵偍偄偰掶惓傪擣傔傞巪偺掶惓怰寛偑側偝傟丄妋掕偟偨偲偒偵偼丄柉帠慽徸朄戞420忦戞1崁戞8崋偺嵞怰帠桼偵側傞偲偄傢側偗傟偽側傜側偄丅 偲偙傠偱丄嵟崅嵸敾強偼丄摉怰偱幚梡怴埬柍岠怰寛偺庢徚惪媮傪棟桼側偟偲偟婞媝偟偨敾寛偺忋崘帠審偵偍偄偰丄偦偺忋崘拞偵摉奩幚梡怴埬偵懳偡傞掶惓怰寛偑妋掕偟偨応崌偵偮偄偰丄塃偺傛偆偵忋崘怰學懏拞偵掶惓怰寛偑妋掕偟偨偲偒偵偼丄 乽尨敾寛偺婎慴偲側偮偨峴惌張暘偼屻偺峴惌張暘偵傛傝曄峏偝傟偨偺偱偁傞偐傜丄 尨敾寛偵偼柉慽朄戞420忦戞1崁戞8崋強掕偺帠桼偑懚偡傞偲偄傢側偗傟偽側傜側偄偑丄偙偺傛偆側応崌偵偼丄尨敾寛偵偮偒敾寛偵塭嬁傪媦傏偡偙偲偺柧傜偐側朄椷偺堘攚偑偁偮偨傕偺偲偟偰偙傟傪攋婞偟丄峏偵怰棟傪恠偔偝偣傞偨傔帠審傪尨怰偵嵎偟栠偡偺偑憡摉偱偁傞乿(徍榓屲嶰擭(峴僣)戞巐幍崋丄徍榓屲巐擭巐寧堦嶰擔敾寛)偲敾寛偟偨丅 塃偺傛偆偵丄搊榐嵏掕偼堦偮偺峴惌張暘偱偁傝丄柍岠怰敾偼塃偺峴惌張暘傪慜採偲偟偰怰棟偣傜傟傞傕偺偱偁傞偑丄摉奩搊榐嵏掕偵傛偮偰幚梡怴埬偲側偮偨柧嵶彂枖偼恾柺偑掶惓怰寛偵傛偮偰掶惓偣傜傟偨偲偒偼丄摉奩幚梡怴埬偺婅彂偵揧晅偝傟偨柧嵶彂枖偼恾柺偼丄塃偺掶惓偣傜傟偨偲偍傝摿嫋弌婅丄弌婅岞崘丄弌婅岞奐丄摿嫋傪偡傋偒巪偺嵏掕枖偼怰寛媦傃幚梡怴埬尃偺愝掕偺搊榐偑偝傟偨傕傔偲傒側偝傟傞偺偱偁傞(幚梡怴埬朄戞41忦偑弨梡偡傞摿嫋朄戞128忦)丅姺尵偡傟偽丄掶惓怰寛偺妋掕偵傛偮偰丄柍岠怰敾偺婎慴偲側偮偨幚梡怴埬尃偺撪梕(尨敾寛偺婎慴偲側偮偨峴惌張暘)偑丄掶惓怰寛偺撪梕偳偍傝曄峏偣傜傟傞偙偲偵側傞偺偱偁傞(屻偺峴惌張暘)丅偟偨偑偮偰丄偙偙偵柉帠慽徸朄戞420忦戞1崁戞8崋偺嵞怰帠桼偑敪惗偡傞偙偲偵側傞偺偱偁傞丅 塃偺偙偲偼丄摉奩帠審偑忋崘怰偵學懏偟偰偄傞応崌偲摉奩帠審偑妋掕偟偰偄傞応崌偵嵎堎偑偁傞傕偺偱偼側偄丅偗偩偟丄慜幰偺応崌偼嵞怰帠桼傪忋崘棟桼偵弨梡偟偰偄傞偺偱偁傝丄屻幰偺応崌偵偙偦杮摉偵嵞怰帠桼傪揔梡偡傞応崌偱偁傞偐傜偱偁傞丅 傕偟掶惓怰寛偑堘朄偲敾抐偝傟丄尨怰寛偑庢徚偝傟偨偲偒偼丄尨敾寛偺婎慴偲側偮偨峴惌張暘偑曄峏偝傟丄柉帠慽徸朄戞420忦戞1崁戞8崋強掕偺帠桼偑敪惗偡傞壜擻惈偑偁傞偙偲偲側傞偺偱偁傞丅偦偟偰丄塃梫審偵奩摉偡傞帠桼偑敪惗偟偨偲偒偵偼丄柍岠怰寛偵偮偄偰嵞怰偑奐巒偝傟傞梫審偵奩摉偡傞偙偲偵側傞偺偱偁傞丅 塃偺傛偆偵嵞怰偺梫審偵奩摉偡傞壜擻惈偑偁傞杮審怰棟偵偮偄偰丄慡偔嵞怰偺壜擻惈傪嫅斲偡傞峫偊曽偼丄嬶懱揑懨摉惈傪廳傫偠嵞怰惂搙傪嵦梡偟偨朄偺庯巪偵斀偡傞偙偲偵側傞丅 (嶰) 杮審偵偍偄偰掶惓怰敾偺惪媮傪擣傔側偐偮偨杮審怰寛偺庢徚傪媮傔傞偙偲偵慽偺棙塿偑偁傞偲傒傞傋偒偙偲偼丄嵟崅嵸敾強偵偍偗傞帠審張棟偺宱夁偐傜傕柧傜偐偱偁傞丅偡側傢偪丄杮審掶惓傪擣傔側偄偲偟偨怰寛偼徍榓巐敧擭敧寧擇嶰擔偵側偝傟丄堦曽幚梡怴埬搊榐傪柍岠偲偡傞怰寛偼徍榓巐嬨擭堦寧嶰堦擔偵側偝傟偨傕偺偱偁傞偲偙傠丄搶嫗崅摍嵸敾強偼丄徍榓屲擇擭堦仜寧擇嬨擔丄杮審掶惓怰寛庢徚惪媮帠審偵偮偄偰偼暿巻掶惓栚榐(2)側偄偟(7)偺掶惓偵娭偡傞晹暘偺怰寛傪庢徚偡巪偺敾寛傪側偡偲偲傕偵丄摨擔柍岠怰寛庢徚惪媮帠審偵偮偄偰偼丄尨崘偺惪媮傪婞媝偡傞巪偺敾寛傪側偟丄椉帠審偲傕忋崘偺寢壥丄嵟崅嵸敾強戞堦彫朄掛偵學懏偟偨丅偦偟偰丄摨戞堦彫朄掛偼丄杮審掶惓怰寛庢徚惪媮帠審偵偮偄偰偼丄岥摢曎榑傪奐偒徍榓屲屲擭屲寧堦擔丄尨敾寛傪攋婞偟丄杮審傪搶嫗崅摍嵸敾強偵嵎偟栠偡巪偺敾寛傪偡傞堦曽丄塃摨擔柍岠怰寛庢徚惪媮帠審偵偮偄偰偼丄忋崘傪婞媝偟偰幚梡怴埬搊榐傪柍岠偲偡傞怰寛傪妋掕偝偣偨偺偱偁傞丅偙偺傛偆偵丄嵟崅嵸敾強偑杮審傪嵎偟栠偟偨偺偼丄柍岠怰寛偺妋掕屻傕杮審掶惓怰寛偺庢徚傪媮傔傞偲偙傠偺慽偺棙塿偑懚嵼偡傞傕偺偲傒偰偄偨偐傜偱偁傞丅偗偩偟丄旐崘偑庡挘偡傞偛偲偔丄柍岠怰寛偺妋掕偵傛偮偰掶惓怰敾惪媮偼偦偺懳徾傪幐偄丄偦偺怰寛庢徚慽徸偼丄慽偺棙塿傪寚偔偙偲偵側傞偺偱偁傟偽丄嵟崅嵸敾強偲偟偰傕杮審掶惓怰寛庢徚惪媮帠審偵偮偄偰丄尨敾寛傪攋婞偟偨偆偊丄嵎偟栠偟敾寛傪偡傞偙偲側偔尨崘偺惪媮傪戅偗偨偼偢偱偁傞偐傜偱偁傞丅 (巐) 塃偺傛偆偵丄柉帠慽徸朄戞420忦戞1崁戞8崋傪夝偡傞偲偒丄幚梡怴埬朄戞39忦戞4崁偨偩偟彂偼丄柍岠怰寛偑妋掕偟偨偺偪偵偼丄怴偨偵掶惓怰敾偺惪媮偑偱偒側偄庯巪偲夝偡傋偒偱偁偮偰丄婛偵掶惓怰敾偺惪媮偑偁偮偨屻偵柍岠怰寛偑妋掕偟偰傕丄掶惓怰敾偵偮偄偰偺慽偺棙塿偑柍偔側傞傕偺偱偼側偄偺偱偁傞(側偍丄摿嫋挕憤柋壽曇乽偲偮偒傛乿戞敧嬨崋偵傛傞偲慜婰嵟崅嵸敾強偺敾寛傪堷梡偟偰丄乽偦偆偩偲偟偨傜丄柍岠妋掕屻偲偄偊偳傕學懏偡傞掶惓怰敾傪帩懕偡傞棙塿偼懚嵼偟丄懳徾側偟偲偟偰娙扨偵媝壓偼偱偒側偄乿((戞堦擇暸塃偺抜))偲夝庍偟偰偄傞)丅 5 怰寛傪庢徚偡傋偒帠桼怰寛偵偼丄師偺揰偵岆傝偑偁傝堘朄偱偁傞偐傜丄庢徚偝傟傞傋偒偱偁傞丅 (堦) 杮審掶惓怰敾庤懕偵偍偄偰丄堦晹掶惓傪媮傔傞庯巪傪柧帵偡傞偨傔偺曗惓偺婡夛偑擣傔傜傟側偐偮偨揰(1) 杮審慽徸偵偍偄偰丄尨敾寛傪攋婞偟丄杮審傪嵎偟栠偟偨嵟崅嵸敾強偺敾寛偼丄拪徾揑側朄棩榑偺晹暘偵偍偄偰丄 乽乧乧偦傟屘丄偙偺傛偆側掶惓怰敾偺惪媮偵懳偟偰偼丄惪媮恖偵偍偄偰掶惓怰敾惪媮彂偺曗惓傪偟偨偆偊塃暋悢偺掶惓売強偺偆偪堦晹偺売強偵偮偄偰偺掶惓傪媮傔傞庯巪傪摿偵柧帵偟偨偲偒偼奿暿丄乧乧乿偲敾抐偟丄師偄偱丄杮審偵偮偄偰偺嬶懱揑敾抐偵偍偄偰丄乽偦偆偡傞偲丄杮審尨柧嵶彂偺婰嵹傪尨敾寛暿巻栚榐(1)側偄偟(8)(杮敾寛揧晅偺掶惓栚榐(1)側偄偟(8)偲摨偠)偺傛偆偵掶惓偡傞偙偲傪媮傔傞偩偗偱丄偙傟偲暿偵摨栚榐(2)側偄偟(7)偺傛偆偵掶惓偡傞偙偲傪媮傔偰偄側偄偙偲偑婰榐忋柧傜偐側旐忋崘恖偺杮審掶惓怰敾偺惪媮偵偮偒丄乧乧乿偲愢柧偟偰偄傞偺偱偁傞丅 塃偺敾寛偵傛傞偲乽尨敾寛暿巻栚榐(1)側偄偟(8)偺傛偆偵掶惓偡傞偙偲傪媮傔傞偩偗偱丄偙傟偲暿偵摨栚榐(2)側偄偟(7)偺傛偆偵掶惓偡傞偙偲傪媮傔偰偄側偄乿偲愢帵偟丄傑偨丄偙傟傪慜採偲偟偰丄乽塃暋悢偺掶惓売強偺偆偪堦晹偺売強偵偮偄偰偺掶惓傪媮傔傞庯巪傪摿偵柧帵偟偨偲偒偼乿偲愢柧偟偰偄傞偺偱偁傞丅姺尵偡傟偽丄惪媮恖偼(1)側偄偟(8)偺慡晹偵偮偄偰偺掶惓傪媮傔傞偑丄 傕偟丄塃偺掶惓偑摿嫋挕偵偍偄偰擣傔傜傟側偄側傜偽(2)側偄偟(7)偩偗偺堦晹暘偩偗偺掶惓偩偗偱傕傛傠偟偄偱偡傛偲偺庯巪傪摿暿偵柧帵偟偨偲偒偼丄摿嫋挕偼塃偺堦晹掶惓偑擣傔傜傟傞偐偳偆偐偵偮偄偰傕怰棟敾抐偟側偗傟偽側傜側偄偺偱偁傞丅塃偺偙偲偼慜婰堷梡偺偲偍傝丄乽乧乧偙傟偲暿偵摨栚榐(2)側偄偟(7)偺傛偆偵掶惓偡傞偙偲傪媮傔偰偄側偄乿偲擣掕敾抐偟偰偄傞偙偲偵傛偮偰柧傜偐偱偁傞丅杮審嵟崅嵸敾強偺敾寛偵傛偮偰柧傜偐側傛偆偵幚梡怴埬朄戞39忦偺掶惓怰敾偼丄惪媮恖偺摿暿偺怽棫偑偁傟偽丄堦晹偺掶惓怰敾傪擣傔偰偄傞偺偱偁傞丅 偪側傒偵丄塃嵟崅嵸敾強偺敾寛斸昡(柉彜朄嶨帍戞敧嶰姫屲崋戞堦擇擇暸側偄偟戞堦擇屲暸)偵偍偄偰亂A亃巵偼丄師偺偛偲偔巜揈偟偰偄傞丅偡側傢偪丄乽杮審敾寛偼寢嬊丄掶惓怰敾庤懕偵偍偄偰暋悢偺掶惓売強偺拞偵晄揔朄側掶惓売強偑偁傞偲敾抐偟偨応崌偺摿嫋挕偼師偺擛偔慬抲偡傋偒巪傪帵嵈偟偰偄傞傕偺偱偁傞偲偄偊傞丅 懄偪丄偦偺傛偆側応崌摿嫋挕偼丄弌婅怰嵏庤懕偵偍偗傞偲摨偠偔丄惪媮恖偵偦偺巪傪捠抦偟偰堄尒彂採弌偺婡夛傪梌偊(朄41忦丄摿嫋朄164忦)傞偲摨帪偵丄 惪媮恖偑掶惓柧嵶彂偵偮偒慜婰嫋梕斖埻撪偵嵞掶惓偡傞偙偲傪娷傔偨堄枴偺惪媮彂曗惓傪擣傔丄怰棟傪恑傔偨寢壥側偍掶惓売強偺堦晹偵晄揔朄側傕偺偑懚偡傞応崌偵偼丄尨懃偲偟偰慡晹婞媝偺怰寛傪偡傋偒傕偺偱偁傞丅扐偟丄偦偺掶惓偑岆婰偺掶惓偺傛偆側宍幃揑側傕偺偱偁傞応崌偵偼丄椺奜揑偵堦晹擣梕偺怰寛傪偡傋偒応崌偑偁傞丅帶偟偰丄塃惪媮彂曗惓偺拞偵偼暋悢偺掶惓売強偺偆偪偺堦晹偺売強偵偮偄偰掶惓傪媮傔傞庯巪傪摿偵柧帵偡傞応崌傪娷傓丅乿偲偟丄偝傜偵丄乽杮審怰敾庤懕拞偵惪媮彂曗惓偑偍偦傜偔側偝傟側偐偮偨偱偁傠偆偙偲慜婰偺偲偍傝偱偁傞偑丄摿嫋幚柋(擇)偑慜婰偺偲偍傝偱偁偮偨埲忋丄惪媮彂曗惓偑柍帇偝傟偨応崌偺庤懕堘攚偵弨偠偰怰寛偺庢徚偟敾寛偑側偝傟摼側偄傕偺偱偁傠偆偐丅乿偲偄偮偰偄傞丅 塃偺偙偲偐傜傒偰傕丄尨崘偺偙偺揰偺庡挘偼寛偟偰丄尨崘撈帺偺傕偺偱偼側偔丄 杮審嵟崅嵸敾強偺敾寛偵傛偮偰丄帺慠偵撉傒偲傞偙偲偑偱偒傞敾抐傪慜採偲偟偰丄 摉慠偵摫偒弌偝傟偰偒偨庡挘偱偁傞丅 (2) 偲偙傠偱丄摿嫋挕偼掶惓怰敾偵偮偄偰丄乽掶惓傪擣梕偟摼傞晹暘偲擣梕偟摼側偄晹暘偲傪嫟偵掶惓梫巪偵娷傓掶惓偺怰敾偵偍偄偰丄惪媮恖偐傜偺梫巪傪尭弅偟偰掶惓傪擣梕偟摼傞晹暘偵偺傒尷掕偡傞堄巚傪桳偟側偄応崌偵偍偄偰丄偦偺晹暘偺傒偵掶惓傪嫋壜偟丄偦偺懠偺晹暘偺掶惓傪嫋壜偟側偄偲偡傞偵懌傞夝柧偑側偝傟偰偄側偄偺偱丄偙傟傪晄壜偲偡傞摉挕怰敾偺怰寛姷峴乧乧乿(徍榓嶰擇擭怰敾戞堦乑榋崋)偲敾抐偟丄偦偺幚柋偵偍偄偰傕丄妋掕揑偵偦偺堦晹掶惓傪擣傔偰偄側偐偮偨偺偱偁傞(亂B亃摿嫋朄奣愢(戞5斉)戞巐巐堦暸幍峴栚丄敾椺帪曬戞嬨榋幍崋戞巐嬨暸戞堦抜丅)敾椺僞僀儉僘戞巐堦幍崋戞敧屲暸戞巐抜)丅 慜弎偺偲偍傝幚梡怴埬朄39忦偺掶惓怰敾偵偼丄堦晹偺掶惓怰敾偺惪媮偑擣傔傜傟傞偲偡傞偺偑朄偨傞婯斖偱偁傞偵偐偐傢傜偢丄摿嫋挕偼幚梡怴埬朄戞39忦偺1掶惓怰敾偵偼堦晹偺掶惓怰敾偼擣傔側偄偲偟丄偡傋偰偺掶惓怰敾偵偍偄偰傕丄堦晹偺掶惓怰敾傪擣傔偰偄側偐偮偨丅偟偨偑偮偰丄杮審偵偍偄偰傕丄惪媮恖(尨崘)偑杮審掶惓怰敾偺惪媮偵偮偄偰丄傕偟丄惪媮恖偺慡晹偺掶惓怰敾偑擣傔傜傟側偄偺偱偁傟偽丄暿巻掶惓栚榐(2)側偄偟(7)偵偮偄偰偺傒掶惓怰敾傪媮傔傞偲偺摿暿偺怽棫偰傪偟偨偲偒偼杮審掶惓怰敾惪媮偼晄庴棟張暘傪庴偗傞偙偲偑柧傜偐偱偁傞丅 偦偺偨傔丄尨崘偲偟偰傕丄偐偐傞惪媮傪偡傞偙偲偑偱偒側偐偮偨偺偱偁傞丅偟偐偟側偑傜丄尦棃幚梡怴埬朄39忦偼慜婰偺偲偍傝堦晹惪媮傪擣傔偰偄傞偺偱偁傞偐傜尨崘偵偼堦晹惪媮傪偡傞尃棙偑偁偮偨偺偱偁傞丅 偼偨偟偰丄偦偆偱偁傞側傜偽丄尨崘偼丄杮審偵偮偄偰掶惓怰敾偵偍偄偰堦晹惪媮傪柧帵偡傞偨傔偵杮審傪怰敾偺抜奒偵栠偟偰栣偆朄棩忋偺棙塿偑偁傞偺偱偁傞丅姺尵偡傟偽丄怰寛偼丄幚梡怴埬朄戞39忦偺夝庍揔梡傪岆傝丄傂偄偰丄尨崘偺堦晹掶惓惪媮尃傪怤奞偟偨偺偱偁傞偐傜丄塃偺怰敾庤懕偵偍偗傞岆傝偼丄怰寛偺寢榑偵塭嬁傪媦傏偡偙偲偑柧傜偐偱偁傞丅 傛偮偰丄怰寛偼堘朄偲偟偰庢徚偝傟傞傋偒偱偁傞丅 (擇) 掶惓栚榐(7)媦傃(8)偵娭偡傞掶惓怰敾惪媮偺庯巪傪岆偮偰棟夝偟丄 偙偺岆偮偨慜採偵棫偮偰塃偺揰偺掶惓傪幚幙忋乽搊榐惪媮偺斖埻乿傪曄峏偡傞傕偺偲敾抐偟偨揰(1) 柧嵶彂偺乽幚梡怴埬搊榐惪媮偺斖埻乿偵偍偗傞乽摦椡寢崌揰17乿傪乽摦椡傪寢崌偡傞慁夞帺嵼偺摦椡姎崌寢崌晹傪側偡忋壓偵嶱帟幵傪桳偡傞悅捈揱摦幉17乿偲掶惓偡傞偙偲(暿巻栚榐(7))偼丄師偵弎傋傞偲偍傝乽搊榐惪媮偺斖埻乿偺尭弅偵奩摉偟丄乽搊榐惪媮偺斖埻乿傪曄峏偡傞傕偺偱偼側偄丅 (i) 乽搊榐惪媮偺斖埻乿偺婰嵹偐傜傒偰乽摦椡寢崌揰17乿偲偼丄乽偦偺憃曽偺摦椡寢崌揰17乿偺偙偲偱偁傞偑丄偙偺揰偵娭偡傞乽峫埬偺徻嵶側愢柧乿偵偍偗傞婰嵹傪傒傞偲丄憃曽偺揱摦憰抲偺枛抂偼丄儈僣僔儓儞懁偺傕偺偑乽僾乕儕乕14乿偵帄傝丄儕傾乕僔儎僼僩懁偺傕偺偑乽僸僣僠嬥嬶12晬嬤乿偵帄傝丄偦偺椉幰傪寢崌偟偰偄傞偺偑乽慁夞帺嵼偺摦椡姎崌寢崌晹乿偱偁傞丅偦偟偰丄婅彂揧晅偺恾柺(暿巻恾柺嶲徠)戞2恾傪傒傞偲丄偦偺乽慁夞帺嵼偺摦椡姎崌寢崌晹乿偼廲幉偺忋曽偲壓曽偵埵抲偡傞奺擇枃偺嶱帟幵偐傜側傞憡懳峔憿埲奜偵偁傝偊側偄偐傜丄尨柧嵶彂拞丄搊榐惪媮斖埻婰嵹偺乽偦偺憃曽偺摦椡寢崌揰17傪堦乧C乗C偵愝偗偨乿偲偼丄忋曽偺擇枃偺嶱帟幵偺岎揰偲壓曽偺擇枃偺嶱帟幵偺岎揰偲傪C乗C偵愝偗偨偲夝偡傞傎偐側偔丄偦偺傛偆側摦椡寢崌揰偼塃恾柺忋柧傜偐偵忋壓偵嶱帟幵傪桳偡傞悅捈揱摦幉偺椉抂偱偁傞丅偟偨偑偮偰丄乽摦椡寢崌揰17乿傪丄憃曽偺乽摦椡傪寢崌偡傞乧乧乧忋壓偵嶱帟幵傪桳偡傞悅捈揱摦幉17乿偲掶惓偟偰傕丄偙傟偵偼昞尰忋偺嵎堎偑偁傞偺傒偱偁偮偰丄偦偺堄枴偼摨堦偱偁傞丅 傑偨丄塃恾柺偵偍偗傞晞崋乽17乿(摦椡寢崌揰)偺堷弌慄偼丄堦尒乽寢崌巕乿傪巜偟偰偄傞偐偵尒偊傞偑丄乽寢崌巕乿帺懱偼丄乽慁夞帺嵼偺摦椡姎崌寢崌晹偺婡擻傪桳偟側偄(慁夞帺嵼偺摦椡姎崌偼丄嶱帟幵偺嶌梡偵傛傞丅)偐傜丄乽寢崌巕乿傪乽摦椡寢崌揰17乿偲傒傞偺偼懨摉偱側偄偺傒側傜偢丄柧嵶彂偵偍偗傞嶌梡岠壥偵娭偡傞乽寢崌僺儞偺幉怱C乗C慄忋偵寢崌揰17偑愝偗傜傟偰偄傞偐傜丄慁摨帪偵墬偰傕巟忈側偔儕儎乕僔儎僼僩傊摦椡傪揱摦偡傞帠偑弌棃傞丅乿(峛戞擇崋徹戞堦暸塃棑堦嶰峴-堦榋峴栚)偲偺婰嵹偲傕崌抳偟側偄丅 偟偨偑偮偰丄寢嬊晞崌乽17乿偺堷弌慄偼丄乽寢崌巕乿傪巜偡偛偲偔尒偊傞傕丄 尦棃丄柧嵶彂偺婰嵹偵偍偄偰偼丄乽憃曽偺揱摦憰抲傪寢崌偡傞悅捈寢崌慄乿傪巜偡傕偺偱偁傞偲偙傠丄掶惓屻偺搊榐惪媮偺斖埻偺婰嵹偵偍偄偰偼乽忋壓偵嶱帟幵傪桳偡傞悅捈揱摦幉17乿偲偡傞偙偲偵傛偮偰丄乽搊榐惪媮偺斖埻乿傪尭弅偟偨傕偺偱偁傝丄乽搊榐惪媮偺斖埻乿傪曄峏偟偨傕偺偱偼側偄丅 (2) 師偵柧嵶彂偺乽幚梡怴埬搊榐惪媮偺斖埻乿偵偍偗傞乽峩阆婡偲僩儗儔乕傪寢崌偡傞寢崌僺儞13幉怱慄忋C乗C乿傪乽峩阆婡偲僩儗儔乕傪嵍塃孅愜帺嵼偵寢崌偡傞寢崌幉怱慄C乗C忋乿偲掶惓偡傞偙偲(暿巻栚榐(8))偼丄柧嵶彂拞偺偦偺梋偺婰嵹偍傛傃恾柺偺婰嵹偵婎偯偒柧椖偱側偄婰嵹偵偮偄偰側偝傟偨庍柧傕偟偔偼乽搊榐惪媮偺斖埻偺尭弅乿偵奩摉偟丄傕偲傛傝乽搊榐惪媮偺斖埻乿傪曄峏偡傞傕偺偱偼側偄丅偡側傢偪丄尨婰嵹偵乽嵍塃孅愜帺嵼偵寢崌偡傞乿偲壛偊偨偺偼丄柧嵶彂拞乽慁夞偺応崌偼寢崌僺儞13傪巟揰偲偟偰峩阆婡偲僩儗儔乕偼嵍塃孅愜偡傞帠偑弌棃傞乿(峛戞擇崋徹戞堦暸塃棑堦乑峴-堦擇峴栚)偲偺婰嵹偵婎偯偔傕偺偱偁傝丄傕偲偺乽搊榐惪媮偺斖埻乿偺婰嵹偐傜乽僺儞13偺暥帤乿傪嶍彍偟偰丄偦偺慜屻傪乽嵍塃孅愜帺嵼偵寢崌偡傞寢崌幉乿偲懕偗傞傛偆偵掶惓偟偨偺偼丄偙傟偵傛偮偰偦偺峔惉偵曄峏偑惗偠側偄偐傜偱偁傞丅 尦棃丄婡懱A偲婡懱B傪寢崌幉偱夞摦揑偵寢崌偡傞宍懺偲偟偰偼丄幮夛捠擮忋婡懱A偲婡懱B偵愝偗偨寠偵娵偄寢崌幉傪娧捠偡傞偙偲偵傛偮偰側偝傟偰偄傞偺偱偁傝丄偙偺幮夛捠擮忋偺棟夝傪慜採偲偟偰杮審掶惓傪傒傞偲杮審掶惓栚榐(1)媦傃(8)偺掶惓偼丄乽寢崌僺儞13乿偺峔憿偲婡擻偵尷掕傪壛偊傞傕偺偱偁傝丄怰寛偺偄偆傛偆偵乽寢崌僺儞乿側傞尷掕傪夝徚偟偨傕偺偱偼側偄丅 偟偨偑偮偰丄傕偲傕偲乽寢崌僺儞13幉怱慄乿偼丄偦偙偵乽偦偺憃曽偺摦椡乿傪寢崌偡傞悅捈揱摦幉傪廳崌偝偣傞偙偲偵堄枴偑偁傞偨傔丄偦偺悅捈揱摦幉傪乽(峩阆婡偲僩儗儔乕傪嵍塃孅愜帺嵼偵)寢崌偡傞寢崌幉怱慄C乗C忋乿偵愝偗偰傕乽峩阆婡偲僩儗儔乕傪寢崌偡傞寢崌僺儞13幉怱慄忋C乗C乿偵愝偗傞偺偲曄傝偑側偄偐傜偱偁傞丅 側偍丄暿巻掶惓栚榐(1)媦傃(2)側偄偟(6)偺掶惓偼丄偦傟偧傟乽搊榐惪媮偺斖埻乿偺婰嵹傪摨栚榐(8)媦傃7偺偲偍傝掶惓偡傞偙偲偵敽偆乽峫埬偺徻嵶側愢柧乿偺婰嵹偵娭偡傞傕偺偱偁傞((2)乣(5)偼丄岅嬪傪惍棟偟偨傕偺丄 (6)偼掶惓屻偺峔惉偵婎偯偔嶌梡岠壥傪捛壛偟偨傕偺)丅 (3) 怰寛偺擣掕敾抐偺岆傝(堦) 怰寛偼乽摦椡寢崌揰17乿傪乽寢崌巕乿傛傝側傞傕偺偲擣掕偟偰偄傞偑丄 寢崌巕偵偼慜宖乽寢崌僺儞偺幉怱C乗C慄忋偵寢崌揰17偑愝偗傜傟偰偄傞偐傜丄 慁夞帪偵偍偄偰傕巟忈側偔儕儎乕僔儎僼僩僿摦椡傪揱摦偡傞偙偲偑偱偒傞丅乿偲偺柧嵶彂婰嵹偺嶌梡岠壥偑側偄偐傜丄塃偺擣掕偼岆傝偱偁傞丅 (擇) 怰寛偼丄杮審峫埬偼丄掶惓慜偵偍偄偰丄峩阆婡偲僩儗儔乕偑嵍塃偵孅愜偡傞偲偒偺拞怱偲側傞幉怱慄偲丄峩阆婡偲僩儗儔乕傪寢崌偡傞寢崌僺儞13幉怱慄C乗C偲丄摦椡寢崌揰17傪捠傞悅捈揱摦幉偺幉怱慄偲偺嶰偮偺幉怱慄傪堦抳偝偣偨峔惉偱偁傞偲擣掕偟偰偄傞偑丄乽搊榐惪媮偺斖埻乿偵偼偦偺傛偆側婰嵹偼尒摉傜側偄丅偦偺峫埬偺梫巪偵偍偄偰偼丄乽峩阆婡偲僩儗儔乕傪寢崌偡傞寢崌僺儞13幉怱慄忋C乗C乿偵乽偦偺憃曽偺摦椡寢崌揰17乿傪愝偗傞偲偝傟偰偄傞偐傜丄偙偺擇偮偺幉怱慄偺傎偐偵堦抳偡傞偙偲傪昁恵偺梫審偲偡傞幉怱慄偼側偄丅偡側傢偪丄怰寛偑偦傟埲奜偵堦抳偝偣傜傟傞傕偺偲偟偰帵偟偨乽峩阆婡偲僩儗儔乕偑嵍塃偵孅愜偡傞偲偒偺拞怱偲側傞幉怱慄乿偼丄塃偵偄偆乽乧乧寢崌僺儞13幉怱慄乿偲摨堦偱偁偮偰丄峩阆婡偲僩儗儔乕偲偺寢崌偺幉怱偑寢壥偲偟偰椉幰傪嵍塃孅愜夞摦偝偣傞幉怱偲側偮偰偄傞偵偡偓側偄丅偟偨偑偮偰丄怰寛偺塃偺擣掕偼岆傝偱偁傞丅 側偍丄怰寛偼乽寢崌僺儞13幉怱慄C乗C乿偲昞尰偟偰偄傞偑丄乽搊榐惪媮偺斖埻乿偵偼乽寢崌僺儞13幉怱慄忋C乗C乿偲婰嵹偝傟偰偄傞偐傜丄C乗C偼丄寢崌僺儞13偺幉怱慄偦偺傕偺偱偼側偔丄偦偺幉怱慄忋偵廳戜偝傟傞廳捈揱摦幉偺幉怱慄傪巜偡傕偺偱偁傞丅 (嶰) 怰寛偼丄杮審峫埬偺掶惓屻偵偍偗傞峔惉偵傛傞偲丄偦偺掶惓慜丄慜宖偺嶰幉怱慄傪堦抳偝偣傞偨傔偵昁梫偲偝傟偨乽摦椡寢崌揰乿丄乽僺儞13乿媦傃乽摦椡寢崌揰17傪寢崌僺儞13幉怱慄忋偵愝偗偨乿峔惉偑枙徚偝傟偨寢壥丄峫埬偺梫巪偵偼丄幚巤椺偲偟偰塃嶰幉怱慄偑堦抳偟側偄峔惉偺丄偟偨偑偮偰丄恾柺媦傃尨柧嵶彂偵婰嵹偝傟偰偄側偄憰抲傑偱曪娷偝傟傞偙偲偵側傞偲偟偰丄暿巻掶惓栚榐(7)媦傃(8)婰嵹偺掶惓偼幚幙忋乽搊榐惪媮偺斖埻乿傪曄峏偡傞傕偺偱偁傞偲敾抐偟偰偄傞丅 偟偐偟側偑傜丄柧嵶彂偺掶惓偑幚幙忋搊榐惪媮偺斖埻偺曄峏偵摉傞偐斲偐偼偦偺惪媮斖埻帺懱偵偮偄偰敾暿偡傋偒傕偺偱偁傞偐傜丄怰寛偺敾抐偺傛偆偵丄掶惓屻偵偍偗傞峫埬偺梫巪偵恾柺媦傃尨柧嵶彂偵婰嵹偝傟偰偄側偄幚巤椺偑曪娷偝傟傞偲偄偆偩偗偱偼丄慡偔堄枴偑側偄偺傒側傜偢丄師偵弎傋傞偲偍傝丄怰寛偑偦偺幚巤椺偲偟偰憐掕偡傞峩阆婡偵楢寢偡傞僩儗儔乕偺嬱摦憰抲偺峔惉(寢崌僺儞偵傛偮偰峩阆婡偲僩儗儔乕傪嵍塃偵孅愜偟側偄傛偆偵寢崌偡傞偲偲傕偵丄忋壓椉抂偵嶱帟幵傪桳偟丄拞娫偵摦椡寢崌揰傪旛偊偰偄側偄悅捈揱摦幉偺幉怱慄傪拞怱偲偟偰峩阆婡偲僩儗儔乕偑嵍塃偵孅愜偡傞傛偆偵峔惉偟偨峩阆婡偵楢寢偡傞僩儗儔乕偺嬱摦憰抲)傕丄掶惓偵傛偮偰偼偠傔偰峫埬偺梫巪偵曪娷偝傟傞偙偲偵側偮偨偲夝偡傞偺傕岆傝偱偁傞丅偡側傢偪丄 (i) 塃憰抲偺乽寢崌僺儞偵傛偮偰峩阆婡偲僩儗儔乕傪孅愜偟側偄傛偆偵寢崌偡傞乿偲偺峔惉偼丄掶惓偺慜屻偲傕搊榐惪媮偺斖埻偵曪娷偝傟偰偄側偄偐傜丄峫埬偺懳徾奜偲偄偆傋偒偱偁傞丅 (鶤) 摨偠偔乽忋壓椉抂偵嶱帟幵傪桳偡傞乿偲偺峔惉偼掶惓偺慜屻偲傕搊榐惪媮偺斖埻偵曪娷偝傟丄恾柺偵傕婰嵹偝傟偰偄傞丅 (鶥) 摨偠偔悅捈揱摦幉偺乽拞娫偵摦椡寢崌揰傪旛偊偰偄側偄乿偲偺峔惉偼丄掶惓偺慜屻偲傕乽搊榐惪媮偺斖埻乿偵曪娷偝傟偰偄側偄偐傜丄峫埬偺懳徾奜偲偄偆傋偒偱偁傞丅 (鶦) 摨偠偔乽悅捈揱摦幉偺幉怱慄傪拞怱偲偟偰峩阆婡偲僩儗儔乕偑嵍塃偵孅愜偡傞乿偲偺峔惉拞乽峩阆婡偲僩儗儔乕偑嵍塃偵孅愜偡傞乿偺偼丄掶惓慜偵偍偄偰偼乽寢戜偡傞寢戜僺儞乿傪巟揰偲偟丄掶惓屻偵偍偄偰偼乽寢崌偡傞寢崌幉乿傪巟揰偲偡傞傕偺偱偁偮偰丄寢嬊丄偄偢傟偵偟偰傕乽悅捈揱摦幉乿傪巟揰偲偡傞傕偺偱偁傞偐傜丄偙偺乽悅捈揱摦幉乿偼掶惓偺慜屻偲傕偵峩阆婡偲僩儗儔乕傪寢崌偡傞幉偵憡摉偟丄摉慠丄搊榐惪媮偺斖埻偵曪娷偝傟偰偄傞丅 擇 旐崘媦傃旐崘曗彆嶲壛恖偺摎曎暲傃偵庡挘1 惪媮偺尨場1側偄偟3偺帠幚偼擣傔傞丅 2 摨4偺庡挘媦傃摨5偺庢徚帠桼偵偮偄偰偺庡挘偼丄偄偢傟傕憟偆丅 怰寛偺擣掕媦傃敾抐偼偡傋偰惓摉偱偁傝丄壗傜堘朄偺揰偼側偄丅 (杮埬慜偺怽棫偰偺棟桼)(堦) 尨崘偑丄杮審掶惓怰敾惪媮帠審(徍榓巐屲擭怰敾戞嬨巐乑嶰崋帠審)偵偍偄偰掶惓傪媮傔偰偄偨搊榐戞幍堦嶰嬨幍崋幚梡怴埬偼丄乽塃搊榐傪柍岠偲偡傞乿巪偺怰寛(壋戞堦崋徹)偺庢徚偟傪媮傔傞怰寛庢徚惪媮帠審(嵟崅嵸敾強徍榓屲嶰擭(峴僣)戞敧崋帠審)偵偮偄偰徍榓屲屲擭屲寧堦擔丄忋崘婞媝偺敾寛(壋戞嶰崋徹)偑側偝傟偨偙偲偵傛傝丄偦偺搊榐偺柍岠偑妋掕偟偨丅偙傟偵傛偮偰丄杮審搊榐幚梡怴埬偼丄偼偠傔偐傜懚嵼偟側偐偮偨傕偺偲傒側偝傟傞(幚梡怴埬朄戞41忦偱弨梡偡傞摿嫋朄戞125忦)偨傔丄杮審掶惓怰敾偼丄慿媦揑偵偦偺懳徾傪幐偮偨傕偺偱偁傞丅 偟偨偑偮偰丄尰抜奒偵偍偄偰偼丄杮審慽徸偵偍偄偰杮審掶惓怰敾惪媮偵學傞怰寛偺庢徚傪媮傔傞棙塿偑懚嵼偟側偄偙偲偵側傞丅 (擇)(1) 尨崘偼丄幚梡怴埬朄戞39忦戞4崁杮暥偵傛傟偽丄偦偺懳徾傪幐偮偨偲偒偵傕掶惓怰敾偺惪媮偑偱偒傞偙偲偼偄偆傑偱傕側偄偲庡挘偡傞偑丄塃偺婯掕偼丄掶惓怰敾偑幚梡怴埬尃偵偮偄偰柍岠怰敾傪傕偮偰峌寕偝傟傞応崌偺堦偮偺杊塹庤抜偲側傞偲偄偆懁柺傪桳偡傞偙偲偵偐傫偑傒丄柍岠怰敾偑尃棙徚柵屻偵偍偄偰傕惪媮偟摼傞偙偲偲偟偨偙偲(摨朄戞37忦戞2崁)偲偺挷榓傪恾偮偨傕偺偲偝傟偰偄傞丅偙偺庯巪偵徠傜偣偽丄偙偺婯掕偑懳徾偲偟偰偄傞偺偼丄懚懕婜娫枮椆偵傛傞尃棙徚柵偺応崌側偳偁偔傑偱傕夁嫀偵偍偄偰幚梡怴埬尃偑懚嵼偟偰偄偨偙偲偵側傞応崌偱偁傝丄杮審偺傛偆偵幚梡怴埬尃偑慿偮偰弶傔偐傜懚嵼偟側偐偮偨偲傒側偝傟傞(摨朄戞41忦偱弨梡偡傞摿嫋朄戞125忦)柍岠怰寛妋掕屻偺応崌偼娷傑側偄偲夝偡傋偒偱偁傞丅偦偟偰丄塃戞39忦戞4崁偺偨偩偟彂偼丄偙偺偙偲傪擮偺偨傔柧妋偵偟偨傕偺偲夝偝傟傞丅 偟偨偑偮偰丄塃戞39忦戞4崁偺婯掕偼丄慿媦揑偵偦偺懳徾傪幐偮偨応戜偵傑偱掶惓怰敾偑惪媮偱偒傞偲偟偨傕偺偱偼側偄偐傜丄尨崘偺庡挘偼棟桼偑側偄丅 (2) 尨崘偼丄幚梡怴埬朄戞39忦戞4崁偨偩偟彂偺婯掕偼丄柍岠怰敾妋掕屻偵偼丄怴偨偵掶惓怰敾偺惪媮偑偱偒側偄偲偄偆庯巪偵夝偡傋偒偱偁傝丄柍岠怰敾妋掕慜偵婛偵偦偺惪媮偑側偝傟偰偄傞掶惓怰敾偺応崌偵偼揔梡偝傟側偄巪庡挘偡傞丅 偟偐偟側偑傜丄柍岠怰寛妋掕慜偵掶惓怰敾偺惪媮偑側偝傟偰偄傞応崌偱偁偮偰傕丄柍岠怰寛偺妋掕偵傛偮偰丄學懏拞偺掶惓怰敾偼丄掶惓偺懳徾偲側傞尃棙帺懱偑弶傔偐傜懚嵼偟側偐偮偨偙偲偵側傞偐傜(摨朄戞41忦偱弨梡偡傞摿嫋朄戞125忦)丄柍岠怰寛妋掕屻偵掶惓怰敾傪惪媮偡傞応戜偲朄棩揑偵偼慡偔摨條偺忬懺偵側傞傕偺偲偄傢偞傞傪摼側偄丅 偟偨偑偮偰丄柍岠怰寛妋掕慜偵掶惓怰敾偺惪媮偑側偝傟偰偄傞応崌偵傕摉慠戞39忦戞4崁偨偩偟彂偺婯掕偑揔梡偝傟傞偲偄傢側偗傟偽側傜側偄丅 偦傕偦傕塃偺傛偆側怰敾庤懕偵學傞婯掕偼丄惪媮恖偺傒側傜偢怰敾姱傪傕峉懇偡傞傕偺偱偁傞偙偲偼偄偆傑偱傕側偔丄偙偺堄枴偐傜怰敾尃偺惂尷傪撪梕偲偡傞傕偺偲傒傞偙偲偑偱偒傞丅偙偺傛偆偵傒傞偲丄塃婯掕偑柍岠怰寛妋掕屻偼掶惓怰敾偦偺傕偺傪偡傞偙偲偑偱偒側偄偙偲傪婯掕偟偰偄傞偙偲偼柧傜偐偱偁傞丅 偙偺傛偆側梡岅椺偼丄摿嫋朄偵偼悘強偵傒傜傟丄椺偊偽摿嫋朄戞124忦丄戞167忦摍偱乽惪媮偱偒側偄乿偲惪媮恖懁偐傜偺昞尰傪傕偮偰婯掕偟偰偄傞応崌偱偁偮偰傕丄怰棟傗怰敾偵偮偄偰惂尷偟偰偄傞偲夝偝傟傞偺偲摨條偱偁傞(亂C亃傎偐丒弌婅丒怰嵏丒怰敾丒慽徸(摿嫋朄僙儈僫乕(2))戞榋嬨嬨暸嶲徠)丅 偙偺揰偵偮偒丄尨崘偼丄幚梡怴埬朄戞39忦戞4崁偨偩偟彂偵偮偄偰旐崘偺傛偆側夝庍傪嵦傞側傜偽丄柍岠怰敾偲掶惓怰敾偺怰棟偑暪峴偡傞応崌偵偍偄偰偄偢傟偺怰棟傪愭峴偝偣傞傋偒偐偵偮偄偰偺婯掕丄惂栺偑側偄偺偱丄柍岠怰寛偑愭偵妋掕偟偨偲偒偵偼尦棃揔朄偩偮偨掶惓怰敾偺惪媮偵偮偄偰怰敾傪庴偗傞尃棙偑扗傢傟傞偙偲偵側傞偟丄傑偨丄柍岠怰寛妋掕屻偵掶惓傪擣傔傞怰寛偑側偝傟傟偽丄柍岠怰寛偵偮偄偰嵞怰帠桼傪惗偠傞偙偲偵側傞偼偢偺偲偙傠丄嵞怰帠桼傪惗偠偝偣傞摴傪暵偞偡偙偲偵側傞寢壥丄嵞怰惂搙偺懚嵼堄媊帺懱傪媈傢偟偔偡傞偙偲偵側傞巪庡挘偡傞丅 偟偐偟側偑傜丄偦傕偦傕幚梡怴埬朄戞39忦戞4崁偨偩偟彂偺婯掕傪愝偗偨庯巪偼丄傓偟傠丄幚梡怴埬尃偑柍岠偲偝傟偨屻偵偍偄偰掶惓怰敾傪擣傔傞偲偡傞偲丄掶惓怰敾偑偨偝傟偨偙偲偑丄摨朄戞41忦偱弨梡偡傞摿嫋朄戞128忦偲偺娭楢偵偍偄偰丄妋掕偟偨柍岠怰寛偵偮偄偰偺嵞怰帠桼偵側偮偰偔傞偙偲偵傕側傝丄偦偺寢壥偄偨偢傜偵惂搙傪暋嶨壔偡傞偙偲偵側傝偐偹側偄偙偲傪峫椂偟偰丄掶惓怰敾偺杊塹揑婡擻偼幚梡怴埬尃偺柍岠偑妋掕偡傞慜偵尷偮偰擣傔傞傛偆偵偟偨偲偙傠偵偁傞偲偝傟偰偄傞偺偱偁傞(摿嫋挕曇丒岺嬈強桳尃朄拃忦夝愢戞擇榋榋暸嶲徠)丅 偪側傒偵丄壖偵丄尨崘庡挘偺傛偆偵丄惪媮偑埲慜偵側偝傟偰偄傟偽柍岠怰寛妋掕屻偵偍偄偰傕掶惓怰敾傪偡傞偙偲偑偱偒傞偲偡傞偲丄椺偊偽丄掶惓怰敾偵偮偄偰惪媮偳偍傝偺怰寛偑偁傞偲丄婛偵妋掕偟偰偄傞柍岠怰寛偵偮偄偰嵞怰偺栤戣偑惗偠傞偽偐傝偱側偔丄偦偺屻偵峏偵掶惓柍岠偺怰寛偑側偝傟偨応崌傪憐掕偡傞偲丄幚梡怴埬尃偼嵞傃柍岠尨場傪桳偡傞傕偲偺撪梕偵傕偳傞偙偲偵側傞偨傔丄柍岠怰寛偺嵞怰偵傛偮偰慿媦揑偵桳岠偵惉棫偟偨偙偲偵側偮偰偄偨幚梡怴埬尃偵偮偄偰嵞傃嵞怰偺栤戣偑惗偠傞傛偆側偙偲傕峫偊傜傟丄偄偨偢傜偵朄棩娭學傪暋嶨壔偡傞帠懺傪彽棃偡傞偙偲偵側傞偺偱偁傞丅 (3) 尨崘偼丄嵟崅嵸徍榓屲巐擭巐寧堦嶰擔戞擇彫朄掛敾寛(乽摿嫋偲婇嬈乿戞堦擇榋崋戞堦屲暸)傪堷梡偟丄塃敾寛偺榑巪偵廬偊偽丄柍岠怰寛偑妋掕偟偨屻偺杮審帠埬偵偮偄偰傕丄掶惓怰敾偺怰棟傪偡傞偙偲偵傛傝柍岠怰寛偺嵞怰帠桼偑惗偠傞壜擻惈偑偁傞偺偱偁傞偐傜丄偐偐傞壜擻惈傪慡偔斲掕偡傞旐崘偺傛偆側峫偊曽偼丄 嬶懱揑懨摉惈傪廳傫偠嵞怰惂搙傪嵦梡偟偨朄偺庯巪偵斀偡傞巪庡挘偡傞丅 偟偐偟側偑傜丄塃嵟崅嵸敾寛偵學傞帠埬偼丄幚梡怴埬尃傪柍岠偲偡傞怰寛偵學傞慽徸偑枹妋掕側忬懺偱忋崘怰偵學懏拞偵丄柧嵶彂偺掶惓傪擣傔傞怰寛偑妋掕偟偨偲偄偆帠埬偱偁傝丄塃敾寛偼丄柧嵶彂偺掶惓傪擣傔傞怰寛偑妋掕偟偨偙偲偵傛傝丄尨敾寛偺婎慴偲側偮偨峴惌張暘偼屻偺峴惌張暘偵傛傝曄峏偝傟偨偨傔丄尨敾寛偵柉慽朄戞420忦戞1崁戞8崋強掕偺嵞怰帠桼偑懚偡傞偙偲偲側偮偨偙偲偑丄忋崘棟桼偨傞丄敾寛偵塭嬁傪媦傏偡偙偲偺柧傜偐側朄椷堘攚偵摉偨傞傕偺偲偟偰丄尨敾寛傪攋婞偟丄峏偵怰棟傪恠偝偣傞偨傔帠審傪尨怰偵嵎偟栠偟偨傕偺偱偁偮偰丄婛偵愭偵柍岠怰寛偑妋掕偟偰偄傞杮審帠埬偵偼捈愙嶲峫偲側傜側偄丅 (4) 尨崘偼丄嵟崅嵸偑杮審偺嵎偟栠偟敾寛偲柍岠怰寛傪妋掕偝偣傞敾寛傪摨擔晅偗偱側偟偨偙偲傪崻嫆偵嵟崅嵸傕尨崘偺庡挘偡傞傛偆側朄棟傪惀擣偟偰偄傞偲傒傜傟傞巪庡挘偡傞丅 偟偐偟側偑傜丄嵟崅嵸偑丄傕偟尨崘庡挘偺傛偆偵柍岠怰寛偵偮偄偰杮審掶惓怰敾偺寢壥偄偐傫偵傛傝尨崘偵媬嵪偺摴傪梌偊傛偆偲偟偨偺偱偁傟偽丄杮審偵偍偄偰嵟崅嵸偑峴側偮偨傛偆偵柍岠怰寛傪愭偵妋掕偝偣丄掶惓怰敾偺寢壥偄偐傫偵傛傝柍岠怰寛偺嵞怰偵傛傞媬嵪傪峫偊傞偲偄偆傛傝偼丄柍岠怰寛偵學傞慽徸偺怰棟傪帠幚忋拞抐偟丄掶惓怰敾偵學傞慽徸偺寢壥傪懸偮偙偲偵偡傞偺偑帺慠側帠埬張棟偺巇曽偱偁傞偲偄傢側偗傟偽側傜偢丄偙偺傛偆側張棟傪偟側偐偮偨偲偄偆偙偲偼丄嵟崅嵸偼丄摿偵尨崘偑悇應偡傞傛偆側柍岠怰寛偵偮偄偰偺尨崘偺媬嵪傪堄幆偟偰偄側偐偮偨偲傒傞偺偑憡摉偱偁傞丅 (庢徚帠桼(堦)偵偮偄偰) 偙偺揰偵偍偗傞尨崘偺庡挘偼丄梫偡傞偵丄尨崘偼杮審掶惓怰敾(徍榓巐屲擭怰敾戞嬨巐乑嶰崋帠審)偵偍偄偰堦晹掶惓惪媮尃傪桳偟偰偄偨偺偱偁傞偑丄怰寛偼偙傟傪怤奞偟偰怰寛傪壓偟偨偐傜丄偦偺庢徚傪媮傔傞偲偄偆傕偺偱偁傞丅偦偟偰丄偦偺慜採偲偟偰丄杮審偺嵟崅嵸徍榓屲屲擭屲寧堦擔戞堦彫朄掛敾寛偼丄掶惓怰敾偺惪媮恖偑暋悢売強偵傢偨傞掶惓怰敾偺惪媮傪偟偨応崌偵丄慡晹偺売強偺掶惓偑擣傔傜傟側偄側傜偽丄堦晹偺売強偺掶惓偱傕嵎偟巟偊側偄巪傪柧帵偟偨偲偒偵偼丄怰敾姱(崌媍懱傪巜偡丅埲壓摨偠)偼塃偺堦晹掶惓偺壜斲偵偮偄偰傕怰棟敾抐偟側偗傟偽側傜側偄偲敾帵偟偨巪庡挘偡傞丅偡側傢偪丄尨崘偼丄塃嵟崅嵸偺敾寛偼掶惓怰敾偺惪媮偵偍偄偰梊旛揑惪媮傪擣傔偨傕偺偲夝偟偰偄傞偺偱偁傞偑丄尨崘偺塃偺庡挘偼丄塃嵟崅嵸敾寛傪惓夝偟偨偄傕偺偱偁偮偰幐摉偱偁傞丅偡側傢偪丄塃嵟崅嵸敾寛偑丄偄傒偠偔傕敾帵偡傞傛偆偵丄乽幚梡怴埬搊榐傪庴偗傞偙偲偑偱偒傞峫埬偼丄堦屄偺傑偲傑偮偨媄弍巚憐偱偁偮偰幚梡怴埬朄39忦偺婯掕偵婎偯偒幚梡怴埬尃幰偑惪媮恖偲側偮偰偡傞掶惓怰敾偺惪媮偼丄幚梡怴埬搊榐弌婅偺婅彂偵揧晅偟偨柧嵶彂枖偼恾柺(埲壓乽尨柧嵶彂摍乿偲偄偆丅)偺婰嵹傪掶惓怰敾惪媮彂揧晅偺掶惓偟偨柧嵶彂枖偼恾柺(埲壓乽掶惓柧嵶彂摍乿偲偄偆丅)偺婰嵹偺偲偍傝偵掶惓偡傞偙偲偵偮偄偰偺怰敾傪媮傔傞傕偺偵傎偐側傜側偄乿(摨敾寛戞巐挌昞屲峴側偄偟堦乑峴)偐傜丄掶惓怰敾偺惪媮偼丄婛偵搊榐偝傟偨堦屄偺傑偲傑偮偨媄弍巚憐偱偁傞峫埬傪丄掶惓柧嵶彂摍偵帵偝傟偨暿偺堦屄偺峫埬偵抲偒姺偊傞偙偲傪媮傔傞傕偺偱偁偮偰丄幚幙揑偵偼堦庬偺怴婯弌婅偲偄偊傞傕偺偱偁傞丅偟偨偑偮偰丄掶惓怰敾偺惪媮偵偍偄偰丄暋悢偺掶惓柧嵶彂摍傪採帵偟偰戰堦揑偵偦偺掶惓傪媮傔傞偙偲偼傕偪傠傫偺偙偲丄庡埵揑偵堦偺掶惓柧嵶彂摍偺偲偍傝偺掶惓傪媮傔側偑傜丄巕旛揑偵懠偺掶惓柧嵶彂摍偺偲偍傝偵傕掶惓傪媮傔傞偙偲傕丄偨偲偊偦偺梊旛揑惪媮偑庡埵揑惪媮偺堦晹偱偁偮偨偲偟偰傕堦屄偺傑偲傑偮偨媄弍巚憐偱偁傞傋偒峫埬偵偮偄偰暋悢偺媄弍巚憐傪庡挘偡傞偙偲偵側傝嫋偝傟側偄偺偱偁傞丅 塃偺傛偆側掶惓怰敾偺惈奿偵徠傜偣偽塃嵟崅嵸敾寛偑乽惪媮恖偵偍偄偰掶惓怰敾惪媮彂偺曗惓傪偟偨偆偊塃暋悢偺掶惓売強偺偆偪偺堦晹偺売強偵偮偄偰偺掶惓傪媮傔傞庯巪傪摿偵柧帵偟偨偲偒偼奿暿乿(摨敾寛戞巐挌棤榋峴側偄偟幍峴)偲弎傋偨庯巪偼丄曗惓壜擻側斖埻撪偵偍偄偰丄掶惓柧嵶彂摍傪嵞搙掶惓偟偨柧嵶彂摍偵岎姺偟丄摉弶偺惪媮偺堦晹偺売強偵偮偄偰偩偗偺掶惓傪媮傔傞惪媮偵曄峏偟偨応崌偺傒傪憐掕偟偰偄傞偲夝偡傞偺偑惓偟偔丄梊旛揑惪媮傪傕擣傔偨傕偺偲偼摓掙夝偡傞偙偲偼偱偒側偄偺偱偁傝丄偙傟偲堎側傝摨敾寛偑梊旛揑惪媮傪峬擣偟偨偲夝偡傞尨崘偺庡挘偼丄偙偺敾寛傪嬋夝偡傞傕偺偱偁偮偰幐摉偱偁傞偲偄傢側偗傟偽側傜側偄丅 壖偵丄尨崘偑梊旛揑惪媮偑偱偒傞偲偄偆尒夝傪偲傞偺偱偁傟偽丄摿嫋挕偺帠柋庢埖偑尨崘偲堎側傞尒夝偵婎偯偄偰側偝傟偰偄偨偲偟偰傕丄帺屓偺夝庍偵婎偯偄偰梊旛揑惪媮傪側偣偽傛偐偮偨偺偱偁傝丄偙傟偵懳偟偰晄庴棟張暘傪庴偗傟偽偦偺張暘偺庢徚傪媮傔偰憟偆傋偒偱偁偮偨偺偱偁傞偐傜丄梊旛揑掶惓怰敾惪媮偺婡夛偑暿偵扗傢傟偨傢偗偱偼側偔丄偙偺偙偲傪傕偮偰怰寛傪庢徚偡傋偒帠桼偲偡傞偙偲偼偱偒側偄丅 側偍丄尨崘偺墖梡偡傞榑暥偑丄梊旛揑掶惓怰敾惪媮傑偱傕峬擣偟偰偄傞傕偺偲偼夝偝傟側偄偑丄壖偵峬擣偟偰偄傞偺偱偁傟偽丄慜弎偟偨傛偆偵慜婰嵟崅嵸敾寛偺撪梕傪惓偟偔棟夝偟偰偄側偄傕偺偱偁傞丅 偟偐傕丄壖偵丄尨崘偺庡挘偵増偮偰丄怰寛偑庢徚偝傟偨偲偟偰傕丄尨崘偑堦晹惪媮偺庯巪傪柧帵偡傞偨傔偵偼丄惪媮偺庯巪偲偺娭學偱丄怰敾惪媮彂偵揧晅偟偨掶惓柧嵶彂摍傪嵞搙掶惓偟側偗傟偽偨傜側偄(堦晹惪媮偺庯巪傪捈愙偵惪媮偺庯巪拞偵擖傟偰曗惓偡傞偙偲偼惪媮偺梫巪偺曄峏偵奩摉偟丄幚梡怴埬朄戞41忦偱弨梡偡傞摿嫋朄戞131忦戞2崁偺婯掕偵傛傝嫋偝傟側偄丅)偑丄婛偵惪媮岞崘傪偡傋偒巪偺寛掕偺摚杮偑憲払偝傟偰偄傞杮審怰敾偵偍偄偰偼丄尨崘偼丄掶惓柧嵶彂摍傪掶惓偡傞偙偲偑偱偒偢(幚梡怴埬朄戞55忦戞2崁丄摿嫋朄戞17忦戞1崁)丄堦曽丄 掶惓怰敾偵偍偗傞怰棟偺懳徾偼惪媮恖偑惪媮彂偵揧晅偟偨掶惓柧嵶彂摍偺傒偵傛偮偰掕傑傞傕偺偱偁傞偙偲偐傜偡傞偲丄怰敾姱偼偨偩偙偺掶惓柧嵶彂摍偺慡懱偵偮偄偰尨柧嵶彂摍傪掶惓柧嵶彂摍偺偲偍傝掶惓偡傞偙偲偺揔斲傪怰棟敾抐偟摼傞偵偡偓側偄偺偱偁傞偐傜丄怰敾姱帺傜掶惓柧嵶彂摍傪掶惓偡傞偙偲偑偱偒側偄偙偲偼偄偆傑偱傕側偄丅偙偺傛偆側帠懺偼幚梡怴埬朄偺慡偔梊憐偟偰偄側偄偲偙傠偱偁傞丅偟偨偑偮偰丄杮審偵偍偄偰偼丄婛偵尨崘偺偄偆堦晹惪媮傪柧帵偡傞曽朄偼側偄偲偄偆傋偒偱偁傞丅 (庢徚帠桼(擇)偵偮偄偰)(堦) 尨崘偼丄杮審峫埬偵偍偄偰乽摦椡寢崌揰17乿偼嶱帟幵傪忋壓椉抂偵桳偡傞悅捈揱摦幉偺幉怱傪偄偆偲庡挘偡傞丅偟偐偟側偑傜丄偦偺柧嵶彂拞偺搊榐惪媮偺斖埻偵偼乽憃曽偺摦椡寢崌揰17傪峩阆婡偲僩儗儔乕傪寢崌偡傞寢崌僺儞13幉怱慄忋C乗C偵愝偗偨乿偲婰嵹偝傟偰偄傞偺傒偱偁傞偐傜丄偦偺摦椡寢崌揰17偼丄 憃曽偺摦椡傪寢崌偡傟偽懌傝傞偲偲傕偵丄峔惉忋丄埵抲偵偮偄偰乽峩阆婡偲僩儗儔乕傪寢崌偡傞寢崌僺儞13幉怱慄忋C乗C乿偵愝偗傞偲偺尷掕偑偁傞傎偐壗傜尷掕偑側偄丅杮審掶惓怰敾惪媮偺庯巪拞偺乽嶱帟幵傪忋壓椉抂偵桳偡傞悅捈揱摦幉乿(暿巻掶惓栚榐(7)嶲徠)偼丄寢崌僺儞13幉怱慄忋偵摦椡寢崌揰傪愝偗傞偲偄偆峔惉傪旛偊偰偄側偄丅側傞傎偳丄偦偺幉怱偼暯柺恾偵偮偄偰傒偨応崌悅捈揱摦幉偺拞怱偱偼偁傞偗傟偳傕丄偙傟傪摦椡寢崌揰偱偁傞偲偡傞婰嵹偼杮審柧嵶彂媦傃恾柺偵側偄偐傜丄尨崘偺塃庡挘偼幐摉偱偁傞丅 (擇) 尨崘偼丄杮審峫埬偑怰寛偺偄偆嶰幉怱慄傪堦抳偝偣傞峔惉偱偁傞偙偲傪憟偆偑丄 (a)乽峩阆婡偲僩儗儔乕傪寢崌偡傞寢崌僺儞13幉怱慄乿偲乽峩阆婡偲僩儗儔乕偑嵍塃偵孅愜偡傞偲偒偺拞怱偲側傞幉怱慄乿偲偑摨堦偱偁傝丄(b)C乗C偑寢崌僺儞13偺幉怱慄忋偵廳崌偝傟傞悅捈揱摦幉偺幉怱慄偱偁傝丄傑偨丄(c)乽偦偺憃曽偺摦椡寢崌揰17乿偑忋壓偵嶱帟幵傪桳偡傞悅捈揱摦幉偵愝偗傜傟偰偄傞偙偲偼尨崘偺帺擣偡傞偲偙傠偱偁傝丄偙傟傜偺帠幚偵傛傟偽丄摦椡寢崌揰17偑愝偗傜傟偰偄傞悅捈揱摦幉偺幉怱慄偼C乗C慄偱偁傞偲偲傕偵((C))丄偦偺C乗C慄偼寢崌僺儞13偺幉怱慄忋偵廳崌偝傟((b))丄傑偨丄寢崌僺儞13偺幉怱慄偼峩阆婡偲僩儗儔乕偑嵍塃孅愜偡傞偲偒偺拞怱偲側傞幉怱慄偱偁傞((a))偑丄偦偺偙偲偵傛偮偰丄偙傟傜嶰偮偺幉怱慄偼堦抳偡傞偙偲偑柧傜偐偱偁傞丅偦偟偰丄杮審峫埬偵偍偗傞崻杮揑媄弍巚憐偼塃嶰幉怱慄偺堦抳偱偁傞丅 傕偟丄搊榐惪媮偺斖埻偵偍偗傞乽偦偺憃曽偺摦椡寢崌揰17傪峩阆婡偲僩儗儔乕傪寢崌偡傞寢崌僺儞13幉怱慄忋C乗C偵愝偗偨乿偲偺婰嵹偵偮偄偰側偝傟偨暿巻掶惓栚榐(8)偺掶惓偑尨崘偺庡挘偡傞傛偆偵柧嵶彂媦傃恾柺偺婰嵹偵婎偯偔庍柧偱偁傞側傜偽丄杮審峫埬偺掶惓屻偵偍偗傞峔惉偼乽寢崌僺儞13乿傪嶍彍偡傞偙偲側偔丄乽偦偺憃曽偺摦椡寢崌揰17傪峩阆婡偲僩儗儔乕傪嵍塃孅愜帺嵼偵寢崌偡傞寢崌僺儞13幉怱慄忋C乗C偵愝偗偨乿偲側傞傋偒偲偙傠丄幚嵺偵偼乽寢崌僺儞13乿傪枙徚偟偰乽偦偺憃曽偺摦椡寢崌揰17傪峩阆婡偲僩儗儔乕傪嵍塃孅愜帺嵼偵寢崌偡傞寢崌幉怱慄C乗C忋偵愝偗偨乿偲偟丄偦偺偨傔丄杮審峫埬偵偍偗傞乽摦椡寢崌揰17傪寢崌僺儞13幉怱慄忋偵愝偗傞乿偲偄偆昁恵偺峔惉梫審傑偱枙徚偝傟偰偟傑偆偙偲偑柧傜偐偱偁偮偰丄偦偺峫埬偺梫巪偼丄慜宖偺嶰偮偺幉怱慄偺堦抳偲偄偆杮審峫埬偺崻杮揑媄弍巚憐傪銥偔偙偲偵側傞偐傜丄塃掶惓偼幚幙忋乽搊榐惪媮偺斖埻乿傪曄峏偡傞傕偺偱偁傞丅 偙偺揰偵娭偟丄尨崘偼丄婡懱A偲婡懱B傪寢崌幉偱夞摦揑偵寢崌偡傞宍懺偲偟偰偼丄幮夛捠擮忋丄婡懱A偲婡懱B偵愝偗偨寠傪娵偄寢崌幉偱娧捠偡傞偙偲偵傛偮偰幚尰偝傟傞傕偺偲棟夝偝傟傞偐傜丄杮審掶惓栚榐(1)媦傃(8)偺掶惓偼丄乽寢崌僺儞13乿偺峔憿偲婡擻偵尷掕傪壛偊偨傕偺偱乽搊榐惪媮偺斖埻偺尭弅乿偵奩摉偟丄乽寢崌僺儞13乿偺尷掕傪夝徚偟偨傕偺偱偼側偄巪庡挘偡傞偑丄婡懱A偲婡懱B偲傪寢崌偡傞応崌偵丄偨偲偊丄偦傟偑孅愜帺嵼側寢崌偱偁偮偰傕丄昁偢偟傕婡懱A偲婡懱B偲偵愝偗偨寠傪寢崌幉偑娧捠偡傞偲偄偆懺條傪嵦傞傕偺偱偼側偄(椺偊偽丄婡懱A偵愝偗偨撌晹傪婡懱B偵愝偗偨墯晹偵偐傫崌偝偣偰寢崌偡傞偙偲丄偁傞偄偼丄婡懱A丄B偺憃曽偺寢崌晹暘偵墯傒傪愝偗偰丄偙傟傜憃曽偺墯傒偵傛偮偰宍惉偝傟傞嬻娫撪偵媴懱傪偦偆擖偟偰椉幰傪寢崌偡傞偙偲側偳偑峫偊傜傟傞丅)偙偲偼丄婡夿偵娭偡傞忢幆忋柧傜偐偱偁傞丅 偟偨偑偮偰丄杮審曗惓屻偺峫埬偵偍偄偰傕摉慠偵寢崌幉丄姺尵偡傟偽丄寢崌僺儞偑懚嵼偡傞偲偺慜採偵棫偮尨崘偺庡挘偼岆傝偱偁傞丅 側偍丄尨崘偼丄怰寛偑掶惓屻偺峫埬偺梫巪偵偼尨柧嵶彂偵婰嵹偺側偄幚巤椺偑曪娷偝傟傞偲偟偰偦偺掶惓偺揔斲傪専摙偟偰偄傞偺偼堄枴偑側偄偲庡挘偡傞偑丄怰寛偼丄杮審峫埬偵偍偗傞乽摦椡寢崌揰17傪寢崌僺儞13幉怱慄忋偵愝偗傞乿偲偄偆昁恵偺峔惉梫審偑枙徚偝傟偨掶惓屻偵偍偗傞偦偺搊榐惪媮偺斖埻偺婰嵹偵偼丄偦偺夝庍忋丄掶惓慜偵偍偗傞慜宖偺乽嶰幉怱慄偺堦抳乿偲偄偆媄弍巚憐傪銥偒丄尨柧嵶彂媦傃恾柺偵婰嵹偺側偄幚巤椺傪娷傓偙偲偵側傞偺偱丄塃掶惓偵傛傝搊榐惪媮偺斖埻偑幚幙忋曄峏偝傟傞傕偺偲敾抐偟偰偄傞偺偱偁偭偰丄塃敾抐偼傕偲傛傝惓摉偱偁傞丅 棟 桼堦 惪媮偺尨場1側偄偟3(摿嫋挕偵偍偗傞庤懕偺宱堒丄杮審峫埬偺梫巪媦傃怰寛偺棟桼偺梫巪)偵娭偡傞帠幚偼丄摉帠幰娫偵憟偄偑側偄丅 擇 偦偙偱丄傑偢丄杮埬慜偺峈曎偵偮偄偰敾抐偡傞丅 塃憟偄偺側偄帠幚媦傃惉棫偵憟偄偺側偄壋戞堦側偄偟戞巐崋徹偵傛傟偽丄徍榓巐嶰擭堦寧擇巐擔偵杮審幚梡怴埬搊榐偺柍岠怰敾偑惪媮偝傟丄徍榓巐嬨擭堦寧嶰堦擔偵乽杮審幚梡怴埬偺搊榐傪柍岠偲偡傞丅乿巪偺柍岠怰寛(埲壓丄乽柍岠怰寛乿偲偄偆丅)偑側偝傟丄堦曽丄徍榓巐屲擭嬨寧堦榋擔偵杮審搊榐幚梡怴埬偺柧嵶彂傪暿巻掶惓栚榐(1)側偄偟(8)婰嵹偺偲偍傝掶惓偡傞偙偲傪媮傔偨杮審掶惓怰敾偑惪媮偝傟丄徍榓巐敧擭敧寧擇嶰擔偵乽杮審掶惓怰敾惪媮偼惉傝棫偨側偄丅乿巪偺怰寛(埲壓丄乽杮審掶惓怰寛乿偲偄偆丅)偑側偝傟偨偙偲丄偦偺屻丄柍岠怰寛媦傃杮審掶惓怰寛偵偮偄偰偺庢徚惪媮帠審偑搶嫗崅摍嵸敾強偵學懏偟偨偑丄徍榓屲擇擭堦乑寧堦嬨擔偵丄柍岠怰寛庢徚惪媮帠審偵偮偄偰偼丄乽尨崘偺惪媮傪婞媝偡傞丅乿巪偺敾寛偑丄傑偨杮審掶惓怰寛庢徚惪媮帠審偵偮偄偰偼丄乽暿巻掶惓栚榐(2)側偄偟(7)婰嵹偺掶惓偵娭偡傞晹暘偵偮偄偰杮審掶惓怰寛傪庢徚偡丅乿巪偺敾寛偑側偝傟偨偙偲暲傃偵塃椉帠審偲傕忋崘偝傟偨寢壥丄徍榓屲屲擭屲寧堦擔丄柍岠怰寛庢徚惪媮帠審偵偮偄偰偼丄忋崘婞媝偺敾寛偑偁傝丄偙傟偵傛偮偰杮審幚梡怴埬搊榐傪柍岠偲偡傞巪偺柍岠怰寛偑妋掕偟丄堦曽丄杮審掶惓怰寛庢徚惪媮帠審偵偮偄偰偼丄塃摨擔丄乽尨敾寛傪攋婞偟丄杮審傪搶嫗崅摍嵸敾強偵嵎偟栠偡丅乿巪偺敾寛偑側偝傟偨偙偲偑丄擣傔傜傟傞丅 偲偙傠偱丄旐崘偼丄塃柍岠怰寛偺妋掕偵傛偮偰杮審掶惓怰寛偼慿媦揑偵偦偺懳徾傪幐偮偨巪庡挘偡傞偑丄掶惓怰敾偺惪媮偲柍岠怰寛偲偺娭學傪婯掕偡傞幚梡怴埬朄戞39忦戞4崁偨偩偟彂偼丄柍岠怰寛偺妋掕屻偼怴偨偵掶惓怰敾傪惪媮偡傞偙偲偑偱偒側偄偲偄偆偵偡偓偢丄柍岠怰寛偺妋掕偵傛偮偰偦傟埲慜偵婛偵側偝傟偰偄傞掶惓怰敾偺惪媮偺棙塿傪幐傢偟傔傞庯巪偺傕偺偲偼夝偝傟側偄丅偦偺棟桼偼師偺偲偍傝偱偁傞丅 (1) 掶惓怰敾偺惂搙偼丄幚梡怴埬搊榐惪媮偺斖埻傪尭弅偡傞偙偲側偳偵傛偮偰偡偱偵愝掕搊榐偝傟偨峫埬偑丄杮棃桳岠偲偟偰懚懕偟偆傞晹暘傕娷傔偰慡懱偲偟偰柍岠偲偝傟偰偟傑偆偙偲傪旔偗傞偨傔丄奩幚梡怴埬尃幰偵懳偟偰丄幚梡怴埬搊榐弌婅偺婅彂偵揧晅偟偨柧嵶彂枖偼恾柺(埲壓丄扨偵乽尨柧嵶彂摍乿偲偄偆丅)偺婰嵹傪掶惓怰敾惪媮彂揧晅偺掶惓偟偨柧嵶彂枖偼恾柺(埲壓丄扨偵乽掶惓柧嵶彂摍乿偲偄偆丅)偵抲偒姺偊傞婡夛傪梌偊傞偙偲偵偦偺幚幙揑堄媊偑偁傞傕偺偱偁傝丄塃偺偛偲偒掶惓怰敾惂搙偺婡擻偐傜偺摉慠偺婣寢偲偟偰丄尨柧嵶彂摍偺掶惓傪偡傋偒巪偺怰寛偑妋掕偟偨偲偒偼丄慿媦揑偵丄掶惓柧嵶彂摍偵傛傝幚梡怴埬搊榐弌婅丄弌婅岞崘丄弌婅岞奐丄搊榐傪偡傋偒巪偺嵏掕枖偼怰寛媦傃幚梡怴埬尃偺愝掕偺搊榐偑側偝傟偨傕偺偲傒側偝傟(幚梡怴埬朄戞41忦偱弨梡偡傞摿嫋朄戞128忦)丄偙傟偵傛偮偰丄尨懃揑偵弌婅帪揰偵偍偗傞帠桼傪惪媮偺棟桼偲偡傞柍岠怰敾惪媮偺峌寕偐傜尭弅偝傟傕偟偔偼柧椖偵偝傟偨幚梡怴埬搊榐惪媮偺斖埻偵偍偗傞峫埬傪杊屼偟丄偙傟傪懚懕偝偣傛偆偲偡傞傕偺偱偁傞丅 (2) 偙偺傛偆偵丄掶惓怰敾偼丄柍岠怰敾偵懳偡傞杊屼庤抜偱偁傝丄傑偨丄掶惓怰敾偺怰寛偺寢壥偵傛偮偰幚梡怴埬搊榐惪媮偺斖埻偺婰嵹偑慿媦揑偵曄傢傞偙偲偐傜丄廬慜偺搊榐惪媮偺斖埻傪慜採偲偟偨柍岠怰寛偑暍偊傞偙偲偵側傞偵傕偐偐傢傜偢丄掶惓怰敾庤懕偲柍岠怰敾庤懕偲偼暿屄撈棫偟偨庤懕偲偟偰怰棟偝傟丄掶惓怰敾偲柍岠怰敾偲偑摨帪偵學懏偡傞応崌偵偍偄偰傕丄幚梡怴埬朄戞48忦偺12戞3崁偑弨梡偡傞摿嫋朄戞184忦偺15戞2崁(崙嵺摿嫋弌婅屌桳偺棟桼偵婎偯偔摿嫋偺柍岠偺怰敾)偺偛偲偔掶惓怰敾偺怰寛偑偁傞傑偱柍岠偺怰敾偺怰寛傪偟偰偼側傜側偄偲偡傞傛偆側朄棩揑崻嫆偼側偄(偦偺屻偺掶惓怰寛庢徚惪媮帠審偲柍岠怰寛庢徚惪媮帠審偺怰棟弴彉傪傕娷傔偰丄偄偢傟傪愭偵怰棟偡傞偐偼丄愱傜怰敾姱偺崌媍懱傗嵸敾強偺嵸検偵傑偐偝傟偰偄偰((嵟敾徍榓巐敧擭榋寧堦屲擔敾寛徍榓巐敧擭怰寛庢徚慽徸敾寛廤戞嬨暸))丄掶惓怰敾偺怰棟傕偟偔偼掶惓怰寛庢徚惪媮帠審偺怰棟偑側偝傟側偄偆偪偼丄柍岠怰敾偺怰寛傪妋掕偝偣側偄傛偆側惂搙揑側曐徹偑側偄丅)偐傜丄愭偵柍岠怰寛偑妋掕偡傞応崌偑偁傝偆傞偑丄偦偺応崌偵傕掶惓怰敾偺寢壥掶惓傪擣傔傞巪偺掶惓怰寛偑妋掕偟偨偲偒偵偼丄偦偺掶惓偺岠壥傪弌婅帪傑偱慿媦偝偣傞偙偲偑丄慜婰掶惓怰敾惂搙偺庯巪偵崌抳偡傞丅 (3) 偦偆偡傞偲丄掶惓傪擣傔傞怰寛偑妋掕偟偨偲偒偼丄妋掕偟偰偄傞摿嫋丄幚梡怴埬摍傪柍岠偲偟偨怰寛庢徚惪媮帠審偵偮偄偰偺敾寛偺婎慴偲側偮偨峴惌張暘偼丄屻偺峴惌張暘偵傛傝曄峏偝傟偨傕偺偲偟偰丄塃敾寛偵偼柉帠慽徸朄戞420忦戞1崁戞8崋強掕偺帠桼偑懚偡傞偲偄偆傋偒偱偁傝丄偐偐傞朄棩忋偺棙塿偼掶惓怰敾偺惪媮恖偐傜扗傢傟偰偼側傜側偄(嵟敾徍榓屲巐擭巐寧堦嶰擔敾寛怰寛庢徚慽徸敾寛廤徍榓屲巐擭戞堦乑堦暸嶲徠)丅 埲忋偺偲偍傝丄杮審偺応崌丄幚梡怴埬搊榐傪柍岠偲偡傞巪偺怰寛偑妋掕偟偰傕丄偦偺妋掕慜偵婛偵杮審掶惓怰敾偺惪媮傪偟偰偄偨尨崘偼杮審掶惓怰寛偺庢徚傪媮傔傞朄棩忋偺棙塿傪桳偡傞傕偺偲夝偡傞傪憡摉偲偡傞丅旐崘偺峈曎偼丄棟桼偑側偄丅 嶰 師偵丄怰寛偵偙傟傪庢徚偡傋偒堘朄偺揰偑偁傞偐斲偐偵偮偄偰専摙偡傞丅 1 傑偢丄尨崘偼丄杮審偺嵎栠偟傪柦偠偨嵟崅嵸敾強偺敾寛偼丄掶惓怰敾惪媮恖偑堦晹偺売強偵偮偄偰掶惓傪媮傔傞庯巪傪摿偵柧帵偟偨偲偒偵偼堦晹偺掶惓怰敾惪媮偑側偟偆傞偙偲傪敾帵偟偨傕偺偱偁傝丄尨崘偼杮棃堦晹偺掶惓怰敾傪惪媮偟偆傞尃棙傪桳偟丄怰敾偵偍偄偰堦晹偺掶惓惪媮傪柧帵偡傞偨傔偵丄杮審傪怰敾偺抜奒偵栠偟偰栣偆朄棩忋偺棙塿傪桳偡傞偲偙傠丄杮審掶惓怰寛偼丄幚梡怴埬朄戞39忦偺夝庍揔梡傪岆傝丄堦晹偺掶惓惪媮偺壜斲偵偮偄偰偼壗傜敾抐偡傞偙偲側偔丄尨崘偺掶惓惪媮慡懱偵偮偒丄偦偺掶惓偼擣傔傜傟側偄偲偟偨傕偺偱偁偮偰丄尨崘偺堦晹掶惓惪媮尃傪怤奞偟偨傕偺偱偁傞偐傜堘朄偱偁傞巪庡挘偡傞丅 偟偐偟側偑傜丄尨崘偑巜揈偡傞塃嵟崅嵸敾強偺敾寛偱偄偆偲偍傝丄乽惪媮恖偵偍偄偰掶惓怰敾惪媮彂偺曗惓傪偟偨偆偊塃暋悢偺掶惓売強偺偆偪偺堦晹偺売強偵偮偄偰偺掶惓傪媮傔傞庯巪傪摿偵柧帵偟偨偲偒乿偵偼丄怰寛偵偍偄偰丄偦偺堦晹偺売強偺掶惓偺壜斲偵偮偄偰敾抐傪側偟偆傞傕偺偲夝偣傜傟傞偑丄偦偆偱側偄尷傝丄塃暋悢偺掶惓屄強傪慡懱偲偟偰丄偦偺掶惓偑嫋偝傟傞偐偳偆偐傪敾抐偡傋偒傕偺偱偁傞偲偙傠丄杮審偵偍偄偰尨崘偑暋悢偺掶惓売強偺偆偪堦晹偺売強偵偮偄偰偺掶惓傪媮傔傞庯巪傪摿偵柧帵偟偰偄傞傕偺偲偼擣傔傜傟側偄偐傜丄怰寛偑尨崘偺掶惓惪媮傪慡懱偲偟偰偦偺嫋斲偵偮偄偰敾抐偟偨揰偵壗傜偺堘朄偼側偄丅尨崘偑丄怰敾偵偍偄偰丄堦晹偺掶惓惪媮傪柧帵偡傞偨傔偵丄杮審傪怰敾偺抜奒偵栠偟偰栣偆朄棩忋偺棙塿傪桳偡傞偐偳偆偐偼丄杮審掶惓怰寛偺堘朄丄揔朄傪敾抐偡傞偆偊偱偼壗傜偺娭學傕側偄偲偙傠偱偁傞丅尨崘偺庡挘偼棟桼偑側偄丅 2 師偵丄尨崘偺媮傔傞杮審掶惓偑丄幚幙忋乽幚梡怴埬搊榐惪媮偺斖埻乿傪曄峏偡傞傕偺偱偁傞偐斲偵偮偄偰敾抐偡傞丅(乽摦椡寢崌揰17乿偲乽寢崌僺儞13乿偺媄弍揑撪梕)(堦) 惉棫偵憟偄偺側偄峛戞擇崋徹(杮審幚梡怴埬岞曬)偵傛傞偲丄杮審峫埬偺梫巪偼丄乽幚梡怴埬搊榐惪媮偺斖埻乿偺婰嵹偺偲偍傝丄峩阆婡A偺儈僣僔儓儞偺堦晹傛傝摦椡傪庢弌偟丄峩阆婡壦戜3偺屻曽偵墑挿揱摦偡傞傛偆偵偟丄堦曽丄僩儗儔乕B懁偼丄儕儎乕僔儎僼僩傛傝壦戜8慜曽偺僸僣僠嬥嬶12晬嬤偵帄傞摦椡揱摦憰抲傪愝偗丄偦偺憃曽偺摦椡寢崌揰17傪峩阆婡偲僩儗儔乕偲傪寢崌偡傞寢崌僺儞13偺幉怱慄忋C乗C偵愝偗偨峩阆婡偵楢寢偡傞僩儗儔乕偺嬱摦憰抲(揧晅恾柺嶲徠丅)偱偁傞偙偲偑擣傔傜傟丄偝傜偵丄乽峫埬偺徻嵶側愢柧乿偺棑偵偼丄乽峩阆婡A偲僩儗儔乕B傪寢崌偡傞応崌偼峩阆婡懁偺僸僣僠儃僣僋僗11偵僩儗儔乕懁偺僸僣僠嬥嬶12傪憓擖偟摦椡寢崌揰17偵偍偗傞寢崌巕摨巙偺寢崌偑揔摉偐斲偐傪妋偐傔偰屻丄寢崌僺儞13傪憓擖偡傟偽傛偄丅偙傟偵傛偮偰憱峴偡傞偲偒慁夞偺応崌偼丄寢崌僺儞13傪巟揰偲偟偰峩阆婡偲僩儗儔乕偼嵍塃孅愜偡傞偙偲偑偱偒傞偑丄 峩阆婡傛傝僩儗儔乕傊偺摦椡揱摦憰抲傕丄寢崌僺儞偺幉怱C乗C慄忋偵寢崌揰17偑愝偗傜傟偰偄傞偐傜丄慁夞帪偵偍偄偰傕巟忈側偔儕儎乕僔儎僼僩傊摦椡傪揱摦偡傞偙偲偑偱偒傞丅乿(杮審幚梡怴埬岞曬戞堦暸塃棑榋峴側偄偟堦榋峴)巪偺嶌梡岠壥偵娭偡傞婰嵹偺偁傞偙偲偑擣傔傜傟丄塃奺婰嵹偐傜傒傞偲丄乽摦椡寢崌揰17乿偲乽寢崌僺儞13乿偲偼師偺傛偆側傕偺偲擣傔傜傟傞丅 (嘥) 摦椡寢崌揰17偼丄 (鶣) 峩阆婡偺儈僣僔儓儞偺堦晹偐傜庢傝弌偝傟丄偦偺壦戜3偺屻曽偵墑挿揱摦偝傟傞摦椡傪丄僩儗儔乕懁偺儕儎乕僔儎僼僩傛傝壦戜8偺慜曽偺僸僣僠嬥嬶12晬嬤偵帄傞揱摦憰抲偵揱払偡傞揰偱偁傞偲偲傕偵丄慁夞帪偵偍偄偰僩儗儔乕懁偺揱摦憰抲偵揱払偝傟傞摦椡偺曽岦偑偦偺揰傪拞怱偲偟偰嵍塃偵慁夞偟摼傞傕偺偱偁傝丄 (鶤) 寢崌僺儞13偺幉怱慄忋丄偟偨偑偮偰丄孅愜帪偺拞怱偲側傞幉怱慄忋偵埵抲偡傞傕偺偱偁傞偙偲丅 側偍丄乽摦椡寢崌揰17乿偺嬶懱揑峔惉偼丄塃偺揰偺傎偐乽幚梡怴埬搊榐惪媮偺斖埻乿偺婰嵹忋壗傜尷掕偝傟偰偄側偄丅 (嘦) 寢崌僺儞13偼丄峩阆婡偲僩儗儔乕偲傪寢崌偡傞梫慺偱偁傞偲偲傕偵丄偦偺幉怱慄偑峩阆婡偲僩儗儔乕偑嵍塃偵孅愜偡傞偲偒偺拞怱偲側傞幉怱慄偲堦抳偡傞傕偺偱偁傞偙偲丅 (擇) 偲偙傠偱丄暿巻掶惓栚榐(8)偺婰嵹偺掶惓偼丄慜宖乽幚梡怴埬搊榐惪媮偺斖埻乿偵偍偗傞乽峩阆婡偲僩儗儔乕傪寢崌偡傞寢崌僺儞13傪幉怱慄忋C乗C乿傪乽峩阆婡偲僩儗儔乕傪嵍塃孅愜帺嵼偵寢崌偡傞寢崌幉怱慄C乗C忋乿偵掶惓偡傞傕偺偱偁傝丄傑偨丄摨栚榐嵹(1)婰嵹偺掶惓偑塃(8)偺掶惓偵晬悘偟偰峫埬偺徻嵶側愢柧拞偺岅嬪傪惍棟偡傞傕偺偱偁傞偙偲偼偦偺撪梕偐傜柧傜偐偱偁傞丅 尨崘偼丄塃(8)偺掶惓偼丄柧嵶彂媦傃恾柺偺婰嵹偵婎偯偒柧椖偱側偄婰嵹偺庍柧偵奩摉偡傞偲庡挘偡傞偑丄塃偺掶惓偵傛偮偰丄幚梡怴埬搊榐惪媮偺斖埻偵偍偗傞乽乧乧寢崌偡傞寢崌僺儞13幉怱慄乿偺婰嵹偑乽乧乧嵍塃孅愜帺嵼偵寢崌偡傞寢崌幉怱慄乿偲偺婰嵹偲側傞寢壥丄慜婰杮審峫埬偺梫巪偐傜乽寢崌僺儞13乿側傞梫審偑枙徚偝傟丄偦偺偨傔丄乽寢崌僺儞13乿偺慜帵(嘦)偺媄弍揑堄媊傕幐傢傟傞偙偲偵側傞偙偲偼柧傜偐偱偁傞偐傜丄塃偺掶惓傪傕偮偰尨崘庡挘偺傛偆偵晄柧椖側婰嵹偺庍柧偵偡偓側偄傕偺偲夝偡傞偙偲偼偱偒側偄丅 尨崘偼丄傑偨丄塃偺掶惓偼乽嵍塃孅愜帺嵼偵寢崌偡傞乿偲偄偆尷掕暥尵傪憓擖偟偰乽寢崌僺儞13乿偺峔憿偲婡擻偵尷掕傪壛偊偨傕偺偱乽幚梡怴埬搊榐惪媮偺斖埻偺尭弅乿偵奩摉偡傞傕偺偱偁傞巪庡挘偡傞偑丄乽寢崌僺儞13乿側傞梫審偼枙徚偝傟偰側偔側偮偰偄傞偙偲偼慜弎偺偲偍傝偱偁傞偐傜乽嵍塃孅愜帺嵼偵寢崌偡傞乿偲帤嬪偑乽寢崌僺儞13乿傪尷掕偡傞傕偺偲偄偊側偄偙偲偼柧傜偐偱偁傞丅尨崘偼丄 偝傜偵丄杮審峫埬偵偍偄偰偼乽寢崌僺儞乿傛傝傕乽寢崌僺儞偺幉怱慄忋乿偑峔惉偺昁恵梫審偱偁傞偐傜乽寢崌僺儞13乿傪枙徚偟偰傕丄偦偺峔惉偼曄峏偝傟側偄傕偺偱偁傞偲傕庡挘偡傞偑丄塃掶惓屻偵偍偗傞杮審峫埬偺峔惉忋丄峩阆婡偲僩儗儔乕偲偺寢崌偑椺奜側偔乽寢崌僺儞乿偵傛偮偰峴傢傟傞偙偲偑帺柧偺偙偲偲偼偄偊偢(偙偺嬱摦憰抲偺媄弍暘栰偵偍偄偰丄孅愜帺嵼側寢崌宍懺偲偟偰寢崌僺儞偵傛傞寢崌偟偐峫偊傜傟側偄傕偺偱偼側偄偐傜丄乽寢崌僺儞乿傪懄乽寢崌幉乿偲棟夝偡傞偙偲偼偱偒側偄丅)丄偟偨偑偮偰丄乽嵍塃孅愜帺嵼偵寢崌偡傞寢崌幉怱慄乿偑捈偪偵寢崌僺儞偺幉怱慄偱偁傞偙偲傪堄枴偡傞傕偺偲偼擣傔傜傟側偄偐傜丄尨崘偺塃庡挘偼摓掙嵦梡偡傞偙偲偑偱偒側偄丅 偦偆偡傞偲丄暿巻掶惓栚榐(8)媦傃(1)偺婰嵹偺掶惓偼丄尨崘偑庡挘偡傞傛偆偵幚梡怴埬朄戞39忦戞1崁奺崋偵奩摉偡傞偲傒傞偙偲偼偱偒偢丄傓偟傠丄杮審峫埬偺峔惉偵偍偗傞乽寢崌僺儞13乿側傞尷掕梫審傪夝徚偟偨偙偲偵傛偮偰丄幚幙忋乽幚梡怴埬搊榐惪媮偺斖埻乿傪奼挘偟偨傕偺偲偄偆傋偒偱偁傞丅 3 偦偟偰丄杮審掶惓怰敾偵偍偄偰掶惓傪媮傔傞暿巻掶惓栚榐(1)側偄偟(8)偺婰嵹偼丄幚梡怴埬搊榐惪媮偺斖埻偵幚幙揑塭嬁傪媦傏偡傕偺偱偁傞偐傜丄偙傟傪堦懱晄壜暘偺掶惓帠崁偲偟偰掶惓怰敾偺惪媮傪偟偨傕偺偲夝偝傟傞埲忋丄暿巻掶惓栚榐(2)側偄偟(7)婰嵹偺帠崁偵偮偒敾抐偡傞傑偱傕側偔丄杮審掶惓怰敾惪媮偵學傞掶惓偼丄幚梡怴埬朄戞39忦戞2崁偺婯掕偵堘斀偡傞傕偺偱偁傞丅 塃偲摨巪偺怰寛偺敾抐偼惓摉偱偁傝丄杮審怰寛偵偼壗傜偙傟傪庢徚偡傋偒堘朄偺揰偼側偄丅 巐 傛偮偰丄怰寛偺堘朄傪棟桼偵偦偺庢徚傪媮傔傞尨崘偺杮慽惪媮傪幐摉偲偟偰婞媝偡傞偙偲偲偟丄慽徸旓梡偺晧扴偵偮偄偰峴惌帠審慽徸朄戞7忦丄柉帠慽徸朄戞89忦丄戞96忦偺婯掕傪揔梡偟偰丄庡暥偺偲偍傝敾寛偡傞丅 |
|
| 捛壛 | |
|
掶惓栚榐(1)柧嵶彂拞丄戞擇暸戞嶰峴側偄偟戞巐峴偵傢偨傞乽寢崌偡傞寢崌僺儞偺幉怱慄忋乿傪乽嵍塃孅嬋帺嵼偵寢崌偡傞寢崌幉怱慄忋乿偵掶惓偡傞丅 (2)摨戞擇暸戞巐峴側偄偟戞屲峴偵傢偨傞乽摦椡姎崌寢崌晹傪乽摦椡姎崌寢崌晹傪側偡忋壓偵嶱帟幵傪桳偡傞悅捈揱摦幉乿偵掶惓偡傞丅 (3)摨戞嶰暸戞巐峴偵偍偗傞乽偦偺摦椡寢崌揰17乿傪乽偦偺摦椡傪寢崌偡傞忋壓偵嶱帟幵傪桳偡傞悅捈揱摦幉17乿偵掶惓偡傞丅 (4)摨戞嶰暸戞嬨峴偵偍偗傞乽摦椡寢崌揰17乿傪乽悅捈揱摦幉17乿偵掶惓偡傞丅 (5)摨戞嶰暸戞堦屲峴偵偍偗傞乽寢崌揰17乿傪乽悅捈揱摦幉17乿偵掶惓偡傞丅 (6)摨戞嶰暸戞堦榋峴偵偍偗傞乽慁夞帪乿傪乽岞抦偺帺嵼愙庤偺傛偆偵慁夞妏搙傪嶰乑搙埲撪偵惂尷偝傟傞偙偲側偔嬨乑搙傪墇偊傞傛偆側応崌偱傕妋幚偵摦椡揱払偑峴偊丄戝慁夞帪乿偵掶惓偡傞丅 (7)幚梡怴埬搊榐惪媮偺斖埻偵偍偗傞乽摦椡寢崌揰17乿傪乽摦椡傪寢崌偡傞慁夞帺嵼偺摦椡姎崌寢崌晹傪側偡忋壓偵嶱帟幵傪桳偡傞悅捈揱摦幉17乿偵掶惓偡傞丅 (8)幚梡怴埬搊榐惪媮偺斖埻偵偍偗傞乽峩阆婡偲僩儗儔乕傪寢崌偡傞寢崌僺儞13幉怱慄忋C乗C乿傪乽峩阆婡偲僩儗儔乕傪嵍塃孅愜帺嵼偵寢崌偡傞寢崌幉怱慄C乗C忋乿偵掶惓偡傞丅 <12258-001> |
| 嵸敾姱 | 悪杮椙媑 |
|---|---|
| 嵸敾姱 | 崅椦崕枻 |
| 嵸敾姱 | 廙嫶掕擵 |