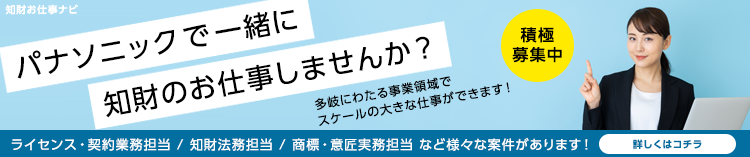| 関連ワード | 技術的範囲 / 禁反言 / 均等 / 考案 / 考案者 / 構造 / 補正 / 拒絶理由 / 削除 / 請求項 / 実施例 / 本質的部分 / 同一の作用効果 / 容易に想到 / 公知技術 / 特段の事情 / 置換 / 数値限定 / 特定 / 明細書 / 請求の範囲 / |
|---|
| 元本PDF |
裁判所収録の全文PDFを見る
|
|---|---|
| 元本PDF |
裁判所収録の別紙1PDFを見る
|
| 事件 |
平成
15年
(ワ)
6742号
製造販売差止等請求事件
|
|---|---|
|
原告 株式会社岩田レーベル 同訴訟代理人弁護士 久世表士 同補佐人弁理士 菅原正倫 同 高野俊彦 被告 朝日印刷株式会社 同訴訟代理人弁護士 大谷典孝 同補佐人弁理士 廣澤勲 |
|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 判決言渡日 | 2004/03/05 |
| 権利種別 | 実用新案権 |
| 訴訟類型 | 民事訴訟 |
| 主文 |
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,原告の負担とする。 |
| 事実及び理由 | |
|---|---|
|
請求
1 被告は,別紙物件目録1(1)記載の包装ラベルを製造し,販売し又は販売の申出をしてはならない。 2 被告は,前項の包装ラベルを廃棄せよ。 3 被告は,別紙物件目録1(2)記載のパンフレットを回収せよ。 4 被告は,原告に対し,金112万5000円及びこれに対する平成15年4月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 |
|
|
事案の概要
1 争いのない事実等 (1) 原告は,レーベル及び包装資材の製造,販売並びにこれに附帯する機械器具の製造,販売等を目的とする会社である。被告は,写真,製版,印刷,製本加工及びその製品の販売並びに包装用品の製造,販売等を目的とする会社である。 (2) 原告は,次の実用新案権(以下「本件実用新案権」といい,実用新案登録請求の範囲請求項1記載の考案を「本件考案」という。)を,リンテック株式会社とともに共有している。 登 録 番 号 第2563899号 考案の名称 包装ラベル付き細口瓶 出 願 日 平成2年10月9日 公 開 日 平成4年5月29日 登 録 日 平成9年11月21日 (3) 本件実用新案権に係る明細書(別紙実用新案登録公報参照。以下「本件明細書」という。甲2)の実用新案登録請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである。 「表面の細口瓶の胴部に相当する位置に印刷層があり,裏面に感圧接着剤層を塗布した熱収縮フイルムであって,該熱収縮フイルムに紫外線吸収剤を含有若しくは塗布し,縦方向の100℃における収縮率が45%以上であり,横方向の100℃における伸縮率が10%以下である熱収縮フイルムの瓶の胴部分に対応する部分と瓶の栓部分に対応する部分との間にミシン目を設けた包装ラベルを細口瓶の胴部に感圧接着剤層で接着させたのち,熱収縮により栓部分に熱収縮フイルムを密着させたことを特徴する包装ラベル付き細口瓶。」 (4) 本件考案は,次のとおり分説される。 A 表面の細口瓶の胴部に相当する位置に印刷層があり, B 裏面に感圧接着剤層を塗布した熱収縮フイルムであって, C 該熱収縮フイルムに紫外線吸収剤を含有若しくは塗布し, D 縦方向の100℃における収縮率が45%以上であり,横方向の100℃における伸縮率が10%以下である熱収縮フイルムの, E 瓶の胴部分に対応する部分と瓶の栓部分に対応する部分との間にミシン目を設けた包装ラベルを, F 細口瓶の胴部に感圧接着剤層で接着させたのち, G 熱収縮により栓部分に熱収縮フイルムを密着させた, H ことを特徴する包装ラベル付き細口瓶。 (5) 被告は,業として,「タックシュリンクラベル」と称する包装ラベル(以下「被告製品」という。)を製造,販売し(甲3,9ないし13,乙1,2の1及び2,15),別紙物件目録1(2)記載のパンフレットを配布して販売の申出をしている(乙3)。 被告製品の構成については,争いがあり,原告は,別紙物件目録1(1)のとおり主張し,被告は,これを否認するが,証拠(甲9ないし13,乙1,13)によれば,別紙物件目録2のとおりであると認められる。 被告製品は,上記構成要件B,E,F及びGを充足する。 2 本件は,原告が,被告製品は,本件考案の各構成要件を充足し,本件考案の実施にのみ使用するものであるから,被告製品を製造,販売等している被告の行為は,実用新案法28条1号の侵害とみなす行為に該当すると主張して,被告に対し,同法27条に基づく被告製品の製造,販売等の差止め,廃棄及びパンフレットの回収並びに不法行為に基づく損害賠償を請求する事案である。 3 争点 (1) 被告製品は,構成要件Cの「紫外線吸収剤を含有若しくは塗布し」を充足するか。 (2) 被告製品は,構成要件Dの「縦方向の100℃における収縮率が45%以上であり」を充足するか。 (3) 被告製品は,本件考案と均等であるか。 (4) 被告製品は,構成要件A及びHの「包装ラベル付き細口瓶」の製造に用いる物であるか。 (5) 損害の発生の有無及びその額 |
|
|
争点に関する当事者の主張
1 争点(1)(紫外線吸収剤)について 〔原告の主張〕 (1) 被告製品は,ラベルにルチル形の酸化チタンを使用している。酸化チタンは,380nm以下の紫外線領域での紫外線吸収率がほぼ80%以上であり,紫外線吸収剤として機能するものである。したがって,被告製品は紫外線吸収剤を含有若しくは塗布しているといえ,構成要件Cを充足する。 被告は,酸化チタンは,白インキに顔料として配合しているもので,紫外線吸収目的はないと主張するが,1つの物質が複数の機能を有することは一般にあり得ることであり,仮に被告製品において,顔料が紫外線吸収以外の目的で配合され,一般的な分類では紫外線吸収剤として分類されないとしても,それが同時に紫外線吸収剤として作用することは否定されないのであるから,紫外線吸収能力を発揮する物質を配合している以上,紫外線吸収剤を含有していることにほかならない。 被告は,被告が使用している酸化チタンは,紫外線散乱剤となるべき超微粒子酸化チタンではなく,粒子径が0.2μmの顔料であるから,紫外線吸収効果はないと主張するが,紫外線防止の技術分野では,散乱とか吸収とかを特に区別する必要はなく同じことであり,広く紫外線吸収剤と称されていて,本件考案にいう紫外線吸収剤も両者を区別する必要はない。酸化チタンが顔料用酸化チタンであっても,超微粒子酸化チタンであっても,本件考案にいう紫外線吸収剤に含まれるのである。 (2) 被告製品は,UV白インキを使用している。UV白インキには,光反応を開始させるための増感剤(被告がいう紫外線硬化剤に相当するもの)が,光重合開始剤として含まれている。紫外線を吸収することにより光増感する増感剤は,紫外線吸収剤として機能するものである。そして,光重合開始剤は,通常のラジカル反応を起こすに十分な量が添加されているから,反応硬化したインキ中には触媒反応していない光重合開始剤は充分残存しており,使用期間中の紫外線からの劣化防止のための吸収機能は保持している。したがって,UV白インキに増感剤が含まれている以上,被告製品は,紫外線吸収剤を含有しているといえる。 (3) 被告製品には,印刷部分のUV白インキだけでなく,透明部分にも紫外線吸収剤が含有されている。このことは,ポリエチレンフイルムには特別な紫外線吸収機能はないにもかかわらず,被告製品のUV白インキ印刷前の原反フイルムは,350nm以下にかけて紫外線を吸収することから明らかである。また,被告製品には容器への粘着剤が塗布されているから,粘着剤に紫外線吸収剤が含有されているとも考えられる。 (4) 被告の主張(4)に対する反論 被告は,酸化チタンを白インキに顔料として配合するため,透明性を有しないと主張するが,本件考案には,「透明」との要件もなければ,印刷部分には白色顔料を入れてはならず,必ず透明でなければならないという特別な要件は存在しない。 本件実用新案権の審査過程においても,紫外線吸収剤に関する審判理由補充書と同じ意見書を提出した後に,拒絶査定を受け,拒絶査定は紫外線吸収剤の要件を理由とされておらず,拒絶理由(乙20)で引用された引用文献3(乙26)も引用文献4(乙27)も理由とされていない。その後の審判では,紫外線吸収剤に関する特別の補正をすることなく,登録が認められている。したがって,本件考案の紫外線吸収剤の要件について,被告が主張するような限定がなされたことを前提として登録されたものではないから,禁反言が適用される余地はない。 審判理由補充書等による原告の主張は,引用文献に記載されている手段が,紫外線を吸収したり散乱したりするものではなく,光を全く通さずに遮断してしまう手段であることを主張したものにすぎず,紫外線吸収機能のある酸化チタン配合UV白インキを除外する主張ではない。被告製品は透明部分もあり,ラベルの上から内容物を確認することも可能であるから,本件考案の紫外線吸収剤を含有するものである。 〔被告の主張〕 (1) 被告製品のラベルにルチル形の酸化チタンが使用されていることは認める。しかし,被告製品は,その使用する白色顔料に白色酸化チタンが含まれているにすぎない。すべての白色インキには酸化チタンが含有されているのであり,被告がことさら,紫外線吸収機能を持たせるために酸化チタンを含有させたわけではない。 紫外線吸収剤とは,有害な紫外線を吸収して無害な振動エネルギーに転換し,それ自身が反応したり分解せずに紫外線吸収作用を永続的に維持可能な物質をいう。可視光を含めた光をすべて遮断する材料を紫外線遮蔽剤というが,紫外線吸収剤は,紫外線のみを吸収して遮断し,可視光を透過させる点で異なる。 被告製品に印刷する白インキには,酸化チタンが顔料として含有されているが,酸化チタン粉末を用いた白色顔料は,紫外線を遮蔽するが,吸収して活性化しないように組成されているのであり,紫外線遮蔽機能は有していても,紫外線吸収剤ではない。 また,酸化チタンを用いた紫外線遮蔽剤は,紫外線散乱剤と称され,これに使用されるのは,10ないし50nm(0.01ないし0.05μm)の超微粒子の酸化チタンである。他方,白色顔料の白色酸化チタンの粒子径は,0.2ないし0.3μmと大きく,紫外線が入射しても紫外線の散乱が生じないため,紫外線領域の光を40%程度透過してしまい,紫外線遮蔽機能が低く,しかも可視光の透過率も60ないし70%と透明性も高くないので,紫外線散乱剤や紫外線遮蔽剤としては用いられない。ただし,顔料チタンの塗膜の厚さを厚くすれば,可視光も含めて遮光することで紫外線の遮断は可能であるが,この場合は,不透明な光遮蔽材というべきであり,本件考案の紫外線吸収剤とは異なる。名古屋市工業研究所作成の成績書(甲27ないし33)において,被告製品のフイルム状供試品の波長が200ないし700nmの紫外線及び全可視光線を含む光の透過率がほとんど0%であることは,被告製品に用いられている白色顔料チタンが,紫外線吸収剤ではなく,光遮蔽材であることを示すものである。 (2) UV白インキとは,印刷インキの乾燥方法の1つとして開発された紫外線乾燥,つまり紫外線硬化型インキの呼称である。UVインキには,紫外線を当てれば直ちに硬化する薬剤(光重合開始剤)が混入されているが,この光重合開始剤は,インキ硬化のためにのみ機能するものであり,硬化によりインキの成分と一体化し,その後に紫外線により反応したり,吸収したりするものではない。したがって,本件考案のように,容器にラベルを貼付した状態で常に紫外線を吸収する紫外線吸収剤とは,その構造及び目的が全く異なるものである。 (3) 被告製品の透明な部分は,白色インキを塗布していないから,酸化チタンも塗布していない。被告製品のフイルム原反の紫外線透過率は,400ないし350nm以上の波長の可視光では,40%程度のフラットな透過率を示し,350ないし300nmにかけて減少し,270nmあたりで0となっているが(甲36ないし39),このような特性は,一般的な紫外線吸収剤を有していないポリエチレンフイルムと同じである(乙39)。多少の違いは,材料や製法,厚さの違い,粘着剤の付着の有無によるものである。逆に,紫外線吸収剤を用いて紫外線透過防止機能を備えたフイルムの場合は,僅かでも紫外線が透過すると実質的な効果が得られないから,紫外線透過率を限りなく0に近づける必要がある。市販の紫外線吸収剤を含むフイルムの場合は,370nm以下の波長の光(紫外線)をほとんど透過せず(乙39,40),被告製品とは異なる。 被告製品においては,粘着剤にも,紫外線吸収剤は添加していない。 (4) 審査官による拒絶理由通知の引用例には,紫外線透過防止機能を備えたシュリンクラベルであって,内面に感熱接着剤が塗布されているものが開示され,また,瓶の側周面が,着色剤を含むインキを印刷等により塗布したシートや顔料をコーティングしたシート等である紫外線遮蔽シートからなる熱収縮性フイルムで被包されている医療用薬液瓶も明示されていた。 原告は,審判請求理由補充書(乙12)において,本件考案は,熱収縮フイルムに紫外線吸収剤を含有若しくは塗布して,瓶自体に紫外線吸収機能を持たせなくても,透明性を維持しながら瓶の内容物を紫外線から保護するものであり,不透明な紫外線遮光機構を備えたものとは異なると主張し,本件考案は,透明な熱収縮フイルムについてのものであるとしている。 したがって,被告製品に使用されている酸化チタン粉末等からなる不透明な白色顔料は,本件考案の紫外線吸収剤ではない。 2 争点(2)(収縮率)について 〔原告の主張〕 (1) 構成要件Dにおける技術的思想の核心的部分は,縦と横の収縮率が大きく異なるという異方性にあるから,「100℃」「45%以上」「10%以下」という具体的数値を満たさなくても,縦横の収縮率の比が45/10以上であれば,被告製品は実質的に構成要件Dを充足する。 ア 被告が提出した100℃での数値(乙3)によっても,被告製品は縦20%の収縮率,横1%の伸縮率を占めるものであるから,縦横の収縮率の比が20となり,構成要件Dの本質である異方性を充分満たすものである。 イ 原告が提出するリンテック株式会社作成の報告書(甲7)によると,被告製品は,100℃のグリセリン浴浸漬加熱温度10秒において縦20%,110℃のグリセリン浴浸漬加熱温度10秒において,縦50%の収縮率を示している。 したがって,約108℃以上になれば,縦45%以上の収縮率となりうる。また,横方向の伸縮率は100℃と120℃の収縮率から推測すると1%程度である。したがって,被告製品は,本件考案と同じ異方性を有し,少なくとも108℃においては,縦45%以上の収縮率を充足する。構成要件中の「100℃」との文言は,100℃付近との目安にすぎず,実際にラベルとして使用する際の加熱温度が220℃という高温で行われることからすれば,20℃前後の温度差は僅差というべきであり,被告製品は実質的に構成要件Dを充足する。 ウ 原告が再度100℃における収縮実験をしたところ,90分加熱すると収縮率が38%に達した(甲15)。また,105℃で10分加熱すると収縮率は43%になり,108℃で10分加熱したところ,収縮率は47%に達した(甲16)。すなわち,100℃で45%には達していないが,その84%強の値に達しており,108℃で47%の収縮を示したのであるから,10分の加熱時間において,被告製品の収縮率が45%に達するのは106ないし107℃であると合理的に推測される。また,乙16の110℃と甲15の100℃における収縮率は同値を示しており,10℃の加熱温度差は公差の範囲であるといえるから,被告製品の熱収縮率が108℃で少なくとも45%以上となるということは,温度公差の範囲内の100℃で45%以上を示すということである。 (2) 仮に,縦の収縮率と横の伸縮率の具体的数値を満たさなければならないとすると,次のような測定方法によるべきである。 ア 測定温度について 本件考案の実施は,必ず100℃で行われなければならないものでもなく,被告の製造ラインでの被告製品の熱収縮は,100℃で実施されていないことは疑う余地がないから,100℃縦45%以上の要件を測定する加熱時間と製造ライン上で商品を製造する際の加熱時間とは全く関係がない。 イ 加熱時間について 本件考案におけるラベルの収縮率は,文字どおり収縮が完了した状態での収縮率(最大収縮率)であり,その収縮率を誤差を抑えて精度良く測定するには,収縮の途中でラベルを取り出してしまわないよう充分長い適切な時間を設定することが求められる。これは,30分,1時間といった長さが充分理由があるところであるが,試験の簡便さ等も考慮して,浸漬時間が10分又は20分に設定されたことは,精度の高い収縮率の測定と試験の簡便さとのバランスに立つ浸漬時間の一例である。その時間は決して長いものではない。 また,そもそもJIS規格は,各種フイルムに応じて加熱温度や浸漬時間を所定の値に選び,収縮率を測定することを定めるもので,加熱温度の120℃や浸漬時間20秒は,一応の基準を例示するにすぎない。そして,JIS規格に一例が示されている120℃ではなく,より低温域である100℃に設定した場合は,20秒という加熱時間は意味がなく,十分な加熱時間による測定が必要である。 (3) 上記(2)を前提として,被告製品の収縮率を測定した結果は,次のとおり,構成要件Dを充足する。 ア リンテック株式会社に試験を依頼し,点眼液の瓶からはがしたラベルによりキャップ部と胴体部の測定用試料を作成し,その試料を100℃に調整されたグリセリン浴に10分間浸漬したときの収縮率を測定した。その結果,測定試料は,キャップ部及び胴体部ともに,その収縮率が縦方向で47%(胴体部は,正しい計算上は52%),横方向で0%であった(甲17)。 また,東京工業大学資源化学研究所a助教授に試験を依頼し,市場より入手したメインター点眼液瓶に装着されているラベル製品の胴部分をはがして所定サイズの試料とし,この試料を100℃に保持したグリセリン中に浸漬し,10分後の収縮率を測定した。結果は,縦の収縮率が43.1%,横の伸縮率が0%であった(甲18)。ラベルは使用済みのものを試料としたので,既に僅かには収縮しているはずであるから,原形寸法は実際は更に大きいはずであり,収縮率の値は実験値よりも増大する。 イ 原告は,市中から入手したメインター点眼液瓶に装着されている被告製品から,ラベルの胴部と栓部をはがし,それぞれについてエチレングリコールの100℃恒温浴槽による収縮実験を愛知県産業技術研究所に依頼した。この結果によれば,メインター点眼液ラベルの胴部で横(フイルムの縦方向)の収縮率が46%,縦(フイルムの横方向)の収縮率が-3%の試験結果が得られ,栓部は同様に44%,-1%であった(甲20)。浸漬時間は10分,エチレングリコールの温度は100℃に保持する設定であるが,実測値として101℃とされた。 ウ 原告は,市中から入手したメインター点眼液瓶に装着されている被告製品のラベル胴部を剥がし,グリセリンの100℃恒温浴槽による収縮実験を大阪府立産業技術総合研究所に依頼した。その結果,グリセリン浴100℃20分の浸漬により,胴部のラベルの収縮率は46.4%であった(甲21)。 エ 原告は,被告製品について気相(熱風)を熱源とする収縮実験を行った。円筒状の疑似容器に対し,その上部から突き出るように,被告製品を円筒状に巻き付け,その状態で,ライスター(熱風機)から熱風をその突き出たラベル上部付近に当て,そのラベル上部を細い円筒状に収縮させる。このときの被告製品の表面温度を直接的に測定するために,示温ラベルと称される温度計をラベルの上部表面に予め貼り,ライスターからの熱風で収縮する被告製品の表面温度を示温ラベルで測定しつつ,上記突き出たラベル部分を収縮させた。その収縮率を測定したところ,92℃から99℃(±1℃誤差を考慮)でそれぞれ3つの試料につき,いずれも縦収縮率48%以上の結果を得た(甲35の1ないし7)。 (4) 被告の実験に対する反論 ア 被告が提出する東京都立産業技術研究所作成の成績書(乙16)の試料1の実験結果においても,浸漬時間が20秒のときに比べて30秒のときは収縮率が急激に増大していることからすると,110℃であれば,44秒足らずで45%の収縮率となることが計算できる。また,測定試料は2枚の金網に挟んで測定されているため,① 金網との物理的接触,② 接着剤による金網との粘着,③ 金網の比熱によるシリコーンオイルの温度低下の各要因が収縮率にマイナスに作用している。一方,試料2は,各温度の収縮勾配から計算すると,100℃にて65秒,105℃にて75秒,110℃にて60秒で45%となる。試料3も同様である。 イ 愛知県産業技術研究所作成の成績書(乙43)については,以下のとおり信用性がない。① デジタル温度計の試験成績書(乙45,46)の記載によれば,いずれも4年ほど前の検定証明であるが,電気測定器のキャリブレーションの有効期間は通常1年であり,精度保持されている証明とはならないし,ガラス管に封入された温度計と異なり,デジタル温度計は設定を変更できるものであり,所有者が被告製品の納品業者である大日本インキ化学工業株式会社であることからも精度の信用性は低い。② 乙43は,愛知県産業技術研究所が被告に試験場所と試験槽を提供して得られたデータを証明するものであって,これをもって第三者機関の証明データとは言い難い。③ 原告は被告製品を市中からしか調達できないが,被告は被告製品を自由に作成できるから,試験に供された試料が被告製品と同一構成のものかは疑問である。④ 乙42において同研究所の立会人であり試験実施者であるとするb主任研究員の署名捺印がなく,信用性がない。 ウ 被告が行った熱風による実験(乙47)は,加熱した所定時間を記載していない。まず,試料と熱風発生器の間隔,熱風発生器の吹き出し温度を試料に貼り付けられた示温ラベルの99℃が黒化しないように設定することで試験準備を整え,その上で所定時間の加熱をして,収縮率を測定すべきである。しかし,被告は,熱風装置をまず200℃に設定し,意図的に示温ラベルが早く黒化するようにして,試験結果を導いたものである。 〔被告の主張〕 (1) 被告製品の縦方向の100℃における収縮率は,45%未満(現実には20%)であるから,構成要件Dを充足しない。これは,従来から被告製品のパンフレットに記載しているところであるが(乙3),被告は,被告の主張に客観性を持たせるため,次の検証を実施した。日本工業規格における収縮包装用フイルムの規格Z1709-1995(以下「JIS規格」という。)では,試験装置を測定温度80ないし160℃の範囲で恒温に保てるものとし,試験方法としては,測定温度の基準を120℃とし,試験片の浸漬時間を20秒を基準としている。これを踏まえて,東京都立産業技術研究所に試験を依頼したところ,100℃の温度において,20秒浸漬した場合の縦方向の収縮率は20%以下であった(乙16)。 なお,原告は,上記の実験方法につき,金網との物理的接触等を主張するが,シリコンオイルの中では,接着剤は粘着しないし,金網による温度低下の点も,十分に大きな恒温油槽を用いており,全く問題ない。2枚の金網の間には,厚さ約3ないし4㎜のスペーサーを挟み込んでおり,これは試料よりはるかに厚いものであるから,フイルムの収縮に何ら影響を与えない。なお,この方法は,JIS規格による測定方法である。 (2) 被告製品のラベルに用いられている熱収縮性フイルムは,基本的に各温度による収縮率は一定であり,浸漬時間に比例して収縮率が上がるものではないが,浸漬中の環境温度が上下している場合,長時間の浸漬においては,その間の最高温度による収縮を示す。したがって,浸漬時間が長いほど,収縮率は,その間の温度むらによる最高温度の影響を受ける確率が高くなり,わずかながら高い値を示す。 しかし,これはあくまでも設定温度により収縮したものではないから,原告の主張する10分等の長時間の浸漬は意味がなく,かえって測定誤差を生じさせる原因となる。 また,浸漬時間に関しては,JIS規格での基準は,20秒であり,フイルムの熱収縮率を利用したラベルが商品として成り立つには,この標準浸漬時間を大幅に超えるようなものでは,製造ラインに乗せることができず,商品とはならない。本件考案も,少なくともこのJIS規格を基準としたものと考えるべきであり,いたずらに浸漬時間を長くし,無理に収縮を待つような考え方は,本件考案の実用性,本質から逸脱した主張である。 (3) 原告の実験に対する反論 ア リンテック株式会社作成の報告書(甲7)の試験に使用された試料(LM151E)は,被告製品に使用するフイルムとは全く無関係であり,被告がこれを使用したことは一切ない。 イ 原告作成の収縮実験結果報告書(甲15)は,いかに浸漬時間をかけようとも,結局45%の収縮率に至らなかったことを示したにすぎない。原告作成の収縮実験結果報告書(甲16)では,加熱温度を100℃以上に上げなければ45%以上の収縮率を上げることができないことを露呈したにすぎない。 ウ 被告製品を製造している大日本インキ化学工業株式会社内で,愛知県産業技術研究所作成の成績書(甲20)と同様な設定により,温度管理を正確に行うことができるオイルバス(東京理化器械社製)を用いて,被告製品について試験を行ったところ,101℃の油温に10分間浸漬しても,28ないし32%の収縮率であった(乙41)。 報告書(乙42)によれば,乙41の試験結果が甲20の試験結果と異なったのは,原告の実験では,制御装置の表示盤の数値を信頼せずに,アルコール温度計により温度管理を行ったため,温度が低く表示されたことが原因であると判明したので,温度管理を試験装置の制御板の設定及び温度制御装置により自動制御し,被告が持ち込んだ検定済みデジタル温度計により,油槽内のエチレングリコールの温度を測定するという条件で,愛知県産業技術研究所で厳密に温度管理して再度試験を行った結果,101℃における被告製品の収縮率は28ないし29%であった(乙43)。 エ リンテック株式会社作成の報告書(甲17),原告補佐人作成の宣誓供述書(甲18)及び大阪府立産業技術総合研究所作成の報告書(甲21)の試験結果も,同様にアルコール温度計により温度を測定しており,温度設定又は管理がずさんであった結果であると考えられる。 リンテック株式会社作成の報告書(甲17)及び原告補佐人作成の宣誓供述書(甲18)において,ビーカー内のグリセリンは,周囲の温度により温められ,上昇し,表面で冷却されて下降する対流を起こしているが,その際のグリセリンの最高温度は,周囲の温度である105ないし107℃であったと考えられる。 オ 原告作成の収縮実験結果(甲35の1ないし7)の熱風による収縮実験は,実験条件があいまいであり,信頼性がない。大日本インキ化学工業により,原告が用いた示温ラベルを被告製品の熱収縮フイルムに付着させ,上記実験と同様の実験を行ったが,99℃を指示する部分まで黒くなったにもかかわらず,被告製品の熱収縮ラベルは,原告の実験と同様の測定方法によれば30%程度の収縮率であり,このときのヒートガンの吹き出し口の熱風温度は200℃であった(乙47)。 3 争点(3)(均等論)について 〔原告の主張〕 被告製品は,たとえ100℃においては縦20%の収縮率でしかないとしても,約108℃以上であれば縦45%以上の収縮率となり得るのであるから(甲7),均等の要件の下で本件実用新案登録請求の範囲に属する。 また,100℃において収縮率43%の試験結果(甲18)が出ていても,45%と43%は僅差であるから,均等の要件の下で本件実用新案登録請求の範囲に属する。 (1) 非本質的部分 本件考案の一要件である収縮率要件の本質は,細口瓶に巻き付ける前に,印刷温度によって実質的に収縮することなく,印刷加熱温度よりも高い温度条件にて,特定の異方性を示すという点である。「108℃」という相違部分は,本件考案の本質的部分ではない。異方性の本質を発揮すべき温度として,8℃という加熱温度差は,ごく僅かな違いにすぎず,作用効果が実質的に同一であれば,この程度の温度差は,何らその本質に問題にならない。実際の生産ラインのラベル化(熱収縮工程)は,熱風機による流れ作業であり,被告製品全体を厳密に100℃の一温度のみになるように温度管理するのは厳密には不可能であり,要求される異方性を保証するために温度範囲があるのは当然である。 (2) 置換可能性 本件考案において,構成要件Dを「縦方向の108℃における収縮率が45%以上であり,横方向の108℃における伸縮率が10%以下である」被告製品に置き換えても,「栓の開封によっても,表示が脱落しない上に,栓部分に皺がない体裁よく包装された包装ラベル付き細口瓶」を提供するという本件考案の目的は,達することができる。その作用機序についても,同一の作用効果を存するものである。 また,被告製品の収縮率が43%だとしても,シュリンクによる同一の作用効果が存在し,45%から43%の収縮率のラベルに置換可能である。 (3) 置換容易性 被告製品に置き換えることは,被告製品の製造時において,容易に想到することができるものである。「その収縮方向に異方性を持たせ,縦方向を45%以上として,横方向を10%以下にする」という本件考案の異方性を,「100℃における」ものとして記載するか,「108℃における」ものとして記載するかは,当業者が適宜行う設計上の微差であり,この変更に困難性は見いだせない。本件考案は,要は印刷温度にて実質的な収縮が起こらず,細口瓶に巻き付けて加熱した際に,本件考案の異方性を発揮できればよいのであり,収縮率は,フイルムの材質や厚さに応じて変化するものであるから,本件特定の異方性を発揮する温度は当業者において適宜調整され得る。 また,45%から43%の収縮率のラベルに置換することも容易である。 (4) 非公知技術 本件考案の出願当時,被告製品に該当する包装ラベル付き細口瓶は存在しておらず,また,当業者が出願時において極めて容易に推考できたものでもない。 すなわち,本件考案の登録請求の範囲において,「100℃における」という部分を「108℃における」,「120℃における」としても登録され得たものである。 なお,印刷ラベルについての異方性を測定するJIS規格は,いまだ存在せず,平成7年に収縮包装フイルムの規格が規定されたにすぎない。収縮包装フイルムは,感圧接着剤層や印刷層がなく,本件の熱収縮性印刷ラベルとは異なる。すなわち,本件考案はパイオニア考案である。 被告が主張する従来技術は,いずれも本件考案とは異なり,本件考案の技術的範囲を制限するものではない。例えば,乙第18号証では,熱収縮開始温度が40ないし65℃であるのに対し,本件考案では70℃以上と完全にずれている。 (5) 特段の事情の不存在 本件考案の出願手続,審査の経過において,被告製品を意識的に除外するなどの特段の事情は存在していない。「100℃における」とは,異方性の本質に鑑みれば,当然に「108℃」や「120℃」で発揮される本件考案の異方性にも解釈されると考えていたものである。また,もとから,「108℃における」や「120℃における」という記載があったものを削除して「100℃における」とした経緯もない。 〔被告の主張〕 (1) 本件考案は,特許庁による審査により2回の拒絶理由通知が出され,いったん拒絶査定となり,不服審判において,本件考案の収縮率の数値,細口瓶との関係,紫外線吸収剤の効果等を主張して初めて登録されたものである。拒絶理由通知書に記載された引用文献には,ポリエステル系収縮フイルムについて,100℃エアーオーブン中5分間処理後の収縮率が,主収縮方向において30%以上,好ましくは40%以上,更に好ましくは40ないし65%の範囲であり,主収縮方向と直交する方向の100℃エアーオーブン中5分間処理後の収縮率は,20%以下,好ましくは15%以下,更に好ましくは10%以下であるとする熱収縮フイルムについて開示されている(乙18)。また,他にも1軸延伸した熱収縮フイルムは開示されている(乙19,21,22,24等)。 したがって,本件考案は,パイオニア的考案ではなく,極めて狭い範囲で限定的に認められた考案であり,100℃で縦方向に45%以上収縮し,横方向の伸縮が10%以下であるという厳格な条件をつけた熱収縮フイルムが本件考案の一構成要件となるにすぎない。したがって,本件考案は,その技術的範囲を数値により特定されたものであるから,この数値を不当に拡大解釈すべきではない。 (2) このように,原告が本件考案の本質であると主張する収縮の異方性は,本件考案の出願当時から周知の事項であり,収縮の異方性が本件考案の本質ではあり得ない。本件考案は,その審査経過のとおり,100℃で縦方向が45%以上の収縮,横方向の伸縮が10%以下の熱収縮フイルムを,細口瓶の胴部から栓にかけて用いる点が1つ重要な要件であり,これを外れることは,本件考案の目的とする作用効果を奏しないものである。 したがって,均等の第1要件は,被告製品には該当せず,被告製品の収縮率は,本件考案の収縮率から外れていることから,被告製品は,意識的に本件考案の技術的範囲から除外されたものであり,第5要件にも該当しない。 (3) 108℃を均等の範囲であるとする原告の主張は否認する。東京都立産業技術研究所作成の成績書(乙16)によれば,110℃でも縦方向の収縮率は30%台であり,明らかに本件考案より小さい。 したがって,均等の第2要件にも該当しない。 (4) 本件実用新案権の出願当時である平成2年10月9日,既に包装材としてのタック性(接着性)とシュリンク性(収縮性),フイルム部分に印刷する方式の乾電池の外包方式が,フイルム・ジャケットとして開発されており,呼称もシュリンク・タックとして公開されていた(乙23)。さらに,被告製品のように,ほぼ円筒状の容器周面に収縮フイルムのラベルを取り付けることは,本件考案の拒絶理由通知書に記載された引用文献(乙19,22。24,25)のとおり,公知のものである。 したがって,被告製品は均等の第4要件にも該当しない。 4 争点(4)(細口瓶)について 〔原告の主張〕 (1) 細口瓶とは,注出口の内径(口内径)が胴部分の直径の70%以下であることを典型事例として想定しており,被告製品が適用される瓶の胴部外径は約19㎜,口内径は約7㎜で,後者の前者に対する比は約37%であるから,被告製品が適用される瓶は細口瓶に該当し,被告製品は構成要件A及びHの「包装ラベル付き細口瓶」の製造に用いる物である。 (2) およそ細口瓶とは,広口瓶に対する名称であって,胴部に対して注出口の内径が一定以上細くなっているものであり,本件考案には,胴体に外径に対して栓(蓋)の外径がいくつでなければならないとの限定はない。① 胴体の外径と栓(蓋)の外径がほとんど変わらない細口瓶で,蓋の上面や胴体の底面に被告製品を回り込ませる場合,② 胴体外径に対して,細口部分にはめる栓(蓋)の外径が小さい場合,③ 栓(蓋)の上部が円錐状になっていて栓外径が変化している場合,④ 胴体外径に変化がある場合,⑤ その他の様々な細口瓶形状に対応して外径が異なる場合に,その外径が異なった部分にも被告製品が密着するような細口瓶であればよいだけのことである。また,見苦しくないように微細な皺をとるために,縦45%以上の応力が発揮され得る状態が好ましいと言っているにすぎず,細口瓶が栓(蓋)の外径によって制限される理由はない。 したがって,被告製品が適用される対象はすべて細口瓶である。 (3) 被告の主張(1)に対する反論 審判請求理由補充書(乙12)4頁の記載は誤記であり,細口瓶の定義は日本薬局方にはない。正しい定義は同10頁の「本願考案は細口瓶の形状,すなわち,細口部分が胴部の70%以下の直径という」である。収縮率と異方性は,粘着剤を塗布した熱収縮性フイルムラベルを皺なく収縮できるという作用効果に必須のものであり,栓外径と胴径の差異に必須のものではない。細口瓶についてそのような限定を条件に特許査定されたのでもないから,禁反言の主張も失当である。 〔被告の主張〕 (1) 原告は,特許庁に提出した審判請求理由補充書(乙12)において,細口瓶とは,栓の外径が胴部の外径の70%以下のものをいうと定義し,構成要件Dに記載された高い収縮率が本件考案の細口瓶において発生する特別な技術的課題を解決するものであると主張している。 しかし,被告製品は,目薬容器等に使用されており,明らかに本件考案の細口瓶とは異なる容器に使用されるものである。甲第10及び第11号証は,栓部分の上部が円錐形状となっているが,これはデザインとしてこのようにしただけであり,細口瓶の範疇に入らない。現にフイルムラベルは,円錐形状部分にまで至らず,単に胴部分と栓部分の同じ外径の部分を包装し,僅かに円錐形状の下部分にフイルムが掛かる程度であり,本件考案の栓の封印と瓶全体の包装とを兼用させた考案とはなっていない。 したがって,被告製品は,構成要件A及びHの「包装ラベル付き細口瓶」の製造に用いる物ではない。 (2) 原告は注出口の内径と胴部分の外径を比較するが,本件考案は,包装方法の1つであり,製品の包装は栓を抜いてすることはあり得ないから,栓部分と胴部分との外径で判断すべきである。 5 争点(5)(損害)について 〔原告の主張〕 被告は,遅くとも平成14年6月から平成15年2月までの間に,被告製品を単価2円50銭で少なくとも100万枚製造,販売しており,利益率は少なくとも45%であるから,112万5000円の利益を得ている。 〔被告の主張〕 原告の主張は争う。なお,実用新案法29条2項による利益は純利益と解されるので,利益率45%という高率な利益はあり得ない。 |
|
|
当裁判所の判断
1 争点(1)(紫外線吸収剤)について (1) 構成要件Cにおける「紫外線吸収剤」の技術的意義 ア 本件明細書の実用新案登録請求の範囲には,「紫外線吸収剤」の意義について記載がなく,考案の詳細な説明には,次の記載がある(甲2)。 (ア) 「本考案に紫外線吸収剤を使用する場合は,フイルム製造時にブレンドすることができる。別法として,熱収縮フイルムの表面又は裏面に紫外線吸収剤を含有するインキを塗布することができる。また,接着剤若しくは印刷インキに紫外線吸収剤をブレンドすることもできる。」(4欄3ないし7行) (イ) 「本考案の熱収縮フイルムに,紫外線吸収剤を塗布若しくはフイルム内にブレンドしたものを使用することができる。塗布する場合は,熱収縮フイルムの表面又は裏面のいずれにも塗布することができる。この紫外線吸収剤の作用によって,紫外線を遮断できるので,瓶の内容物の紫外線による変質を防止することができる。本考案に用いる紫外線吸収剤は紫外線を吸収して内容物の変質を防止するものであり,例えばヒドロキシベンゾフェノン類,ベンゾトリアゾール類,サリチル酸エステル類及びアクリロニトリル誘導体類などを好適に使用することができる。」(4欄35ないし45行) (ウ) 「紫外線吸収剤を使用すれば,瓶を例えば茶色に着色する必要がなく,内容物を透明な瓶の外から確認することができる利点がある。」(4欄46ないし48行) (エ) 「また,紫外線吸収剤を適用することができ,透明な瓶の使用が可能となるので,内容物の変質の発見が容易であり,かかる利点は薬瓶の包装ラベルにおいて特に有用である。」(6欄20ないし23行) イ また,原告が特許庁に提出した拒絶査定に対する審判請求理由補充書(乙12)には,引用文献3(乙26)及び引用文献4(乙27)との関係について,次の記載がある。 (ア) 「また,引用文献3の紫外線防止作用は,紫外線吸収剤によるものではなく,単なる遮光性を付与した場合の当然の作用効果として,熱収縮フイルムの紫外線防止機構が開示されていますが,紫外線吸収剤の構成はありません。まして,紫外線防止剤を含有させて,透明性を維持しながらの瓶内容物を紫外線から防止する記載はありません。・・・の記載から考えると,引用文献3の紫外線透過防止機能は,ラベルを不透明化する遮光機構であると考えられます。本願考案における紫外線吸収剤とはまったく相違する構成が記載されているに過ぎません。」(12頁6ないし17行) (イ) 「一方,引用文献4には,紫外線遮断シートが記載されていますが,この紫外線遮断シートには,紫外線阻止剤が配合されているシート,着色剤を含む印刷シート,顔料をコーティングしたシート,アルミニウムを蒸着したシート等が例示されています。従って,この具体例から見ると,紫外線阻止剤を配合したシートも,紫外線吸収剤を配合した本願考案の透明な熱収縮フイルムとは概念が相違するものと認定することができます。このような概念の相違する考案における紫外線阻止剤の中から紫外線吸収剤による構成を特定することは当業者が極めて容易になし得ない構成と認定することができます。」(12頁18ないし25行) (ウ) 「その上,引用文献4の記載に基づき,多種の紫外線防止手段から透明性を維持する紫外線吸収剤による紫外線防止効果を選択することも当業者にとって極めて容易になし得ることでないと思考します。引用文献3には,紫外線吸収剤の構成は存在しません。」(13頁9ないし12行) ウ 日本化学会編「化学便覧(改訂3版)」(昭和55年発行。乙34)には,紫外線吸収剤とは,紫外線によるプラスチック,ゴムなどの劣化を防ぐため添加される物質であって,光化学的に有害な300ないし400nmの紫外線を吸収して大部分を熱エネルギーに変換し,放散するものであり,紫外線吸収剤必要特性として,400nm以下の光を吸収して,それ自身光に対して安定であると同時に,可視光を吸収しないことが必要である旨記載されている。 また,紫外線吸収剤の特徴としては,① 最大吸収波長が320ないし350nmにあり,プラスチック等の熱可塑性樹脂が最も影響を受ける300ないし400nmの紫外線を吸収すること,② 該吸収剤自身が,熱や光に対して安定であること,③ ベンゾトリアゾール系,ベンゾフェノン系がよく使用されており,幅広い種類の樹脂に使用されること,④ ヒンダードアミン系との併用により相乗効果が期待できること,⑤ ボトルなどに添加され,内容物の変質防止にも寄与することが挙げられる。その作用機構は,プラスチック等の熱可塑性樹脂に有害な紫外線を吸収して,無害な運動エネルギー,熱エネルギーに変換して効果を発揮することである(乙35)。 さらに,「剤」とは,一般的に,作用させる特定の物質に対して特定の効果を与えることを目的として,その特定の効果を顕著に奏するように適用されるものを意味するのであるから,「紫外線吸収剤」は,上記のような紫外線吸収効果を与えることを目的として,紫外線吸収効果を顕著に奏するように適用されるものをいうと解すべきである。 エ 上記ア(ウ)(エ)のとおり,本件明細書には,紫外線吸収剤を適用することにより透明な瓶の使用が可能となること及び内容物を透明な瓶の外から確認することができることを本件考案の効果として挙げていること,上記イ(ア)ないし(ウ)のとおり,拒絶査定に対する審判請求理由補充書において,引用文献3(乙26)に記載される遮光機能によって紫外線を防止するものや,引用文献4(乙27)に例示される着色剤・顔料を添加,アルミニウムの蒸着によって紫外線を防止するものとは,ラベルの透明性を維持しながら紫外線を防止する点によって区別されることを強調して本件実用新案権を取得していることを総合すれば,本件考案における「紫外線吸収剤」とは,それを含有させてラベルの透明性を維持し得るものに限定されると解される。 オ 以上を総合すると,本件考案における「紫外線吸収剤」に該当するためには,前記ウで認定した一般的な紫外線吸収剤の特徴を充たしながら,それを含有させてラベルの透明性を維持し得るものであること,すなわち,① 400nm以下の光を吸収し,大部分を熱エネルギーに変換して放散するものであって,それ自身光に対して安定であると同時に,可視光を吸収しないことを目的とし,そのような紫外線吸収効果をフイルム自体,あるいはこれに塗布する接着剤若しくはインキに対して,顕著に奏するように適用されるものであって,かつ,② ラベルの透明性を維持し得るものであることを要するというべきである。 (2) 被告製品の酸化チタンについて 被告製品は,そのラベルの白色部分にUV白インキを使用しており,UV白インキ中には酸化チタンが使用されている。原告は,酸化チタンは,380nm以下の紫外線領域での紫外線吸収率がほぼ80%以上であり,紫外線吸収剤として機能するから,上記酸化チタンが構成要件Cの「紫外線吸収剤」に当たる旨主張する。 ア 酸化チタンには,ルチル形とアナタース形があるが,ルチル形の方が屈折率が大きいため,隠蔽力,着色力はアナタース形より優れており,被告製品のUV白インキも,ルチル形の酸化チタンを使用している(乙8の2の1及び2)。酸化チタンは,波長200ないし380nmの紫外線領域の紫外線に対し,ほぼ80%以上と良好な吸収性を有するので,物質の一般的性質としては,紫外線吸収機能を有するものである(甲5,6)。 イ しかしながら,顔料用に使用される酸化チタンと紫外線吸収剤として使用される酸化チタンは,それぞれの目的とする効果に応じて粒子径と製造方法が異なる。顔料用酸化チタンの粒子径は,光の散乱が最大となるように,光の波長の2分の1の粒子径0.2ないし0.3μmとなるように設計しているのに対し(甲6),紫外線吸収剤として使用される酸化チタンの粒子径は,その10分の1の10ないし50nmの超微粒子となっている(乙8の2の1及び2)。 したがって,被告製品に使用されている酸化チタンは,紫外線吸収剤として使用される酸化チタンよりも,紫外線吸収効果は低く,紫外線吸収効果を与えることを目的として,紫外線吸収効果を顕著に奏するように適用されるものということはできない。 ウ さらに,酸化チタンは,光酸化触媒として紫外線を吸収して周囲の化学物質を分解する機能を有するが,顔料用酸化チタン粉末においては,この光触媒機能がインキ成分等を分解しないよう抑制する必要があるため,光触媒活性の低いルチル形を使用し,酸化チタンの結晶中に亜鉛,アルミニウムイオンを取り込んだり,酸化チタン粒子表面を遮断する目的で,シリカ,アルミナ,チタニア,ジルコニアなどの含水酸化物を組み合わせた無機物表面処理を行っている。すなわち,酸化チタン粉末を用いた白色顔料は,紫外線を吸収して活性化しないように組成されている(甲6,乙8の2の2)。 エ もっとも,顔料用に使用される酸化チタンは,その顔料としての効果に資するため,光の散乱効果を有する。したがって,顔料の塗膜の厚さを厚くすれば,可視光も含めて遮光することで紫外線の遮断は可能である。しかしながら,一般に,紫外線吸収剤と紫外線散乱剤とは区別されているところ(乙32,33),顔料用酸化チタンは,不透明であることによる光遮蔽効果を有するが,紫外線吸収剤とは異なるというべきである。 名古屋市工業研究所による被告製品の紫外線透過率の試験結果(甲27ないし33)によれば,被告製品であるメインター点眼液ラベルの胴部白色部分(酸化チタン含有白色インキ部分)では,一般的な紫外線領域(200ないし380nm程度)のみならず,200ないし700nmの全可視光線を含む光の透過率がほとんど0%となっている。株式会社島津総合分析試験センターによる被告製品の白色部分の透過スペクトルの測定(甲46,47)によれば,400nm以上の可視光を一部透過し,400nm以下の紫外線は透過していないという結果が出ている。しかし,これらは,いずれも紫外線を透過しないというだけであって,紫外線が吸収されたのか散乱されたのか区別がなく,被告製品の白色部分が紫外線吸収剤を含むということを直接立証するものではない。むしろ,上記のとおり,不透明であることからの光遮蔽効果によるものと考えられる。 オ 上記イのとおり,被告製品に使用されている顔料用酸化チタンは,紫外線吸収剤として使用される酸化チタンよりも,粒子径の選択からみても,紫外線吸収効果は低く,また,上記ウのとおり,紫外線を吸収して活性化しないように組成されているから,プラスチックに有害な400nm以下の紫外線を吸収する効果を与えることを目的として,紫外線吸収効果を顕著に奏するように適用されるものとはいえない。 前記(1)オのとおり,本件考案において「紫外線吸収剤」とは,フイルム自体,あるいはこれに塗布する接着剤若しくはインキに対して,紫外線吸収効果を与えることを目的とし,当該紫外線吸収効果を顕著に奏するように適用されるものでなくてはならず,単に,物の固有の性質として紫外線吸収効果があることをもって,「紫外線吸収剤」ということはできない。 したがって,被告製品に含まれる酸化チタンは,紫外線吸収効果を目的として添加されたものではなく,また,上記エのとおり,実際に紫外線吸収効果があることも確認できないのであるから,酸化チタンが一般的性質として有する紫外線吸収機能をもって,被告製品に含まれる顔料としての酸化チタンが本件考案の「紫外線吸収剤」であるとはいえない。 そして,そもそも前記(1)オで認定したとおり,本件考案における「紫外線吸収剤」とは透明性を維持し得るものに限定されると解されるところ,被告製品の白インキに含まれる酸化チタンは,白色であり,透明性を維持するものではないから,この点からしても本件考案における「紫外線吸収剤」であるとはいえない。 (3) 被告製品の光重合開始剤について 被告製品は,そのラベルの白色部分にUVインキを使用しており,UVインキには光重合開始剤が含まれる。原告は,光重合開始剤が紫外線の光エネルギーを吸収することから,上記光重合開始剤が構成要件Cの「紫外線吸収剤」に当たる旨主張する。 ア UVインキとは,紫外線硬化型インキの呼称である。UVインキにおいては,紫外線を照射することにより,インキに含まれている光重合開始剤が紫外線の光エネルギーを吸収してラジカルを生成し,インキのビヒクル成分の重合を進行させ,インキを固化させるものである(乙30)。 すなわち,光重合開始剤は,インキのビヒクルの重合に寄与するものであるから,紫外線吸収を目的とし,紫外線吸収効果を奏するように適用されるものとはいえない。 イ 原告は,硬化したインキ中には,反応していない光重合開始剤が充分残存しており,紫外線吸収機能がある旨主張する。しかしながら,UVインキは,硬化不足又は硬化過度の場合,インキ被膜に欠陥が出やすいという特徴があるので(乙30),反応硬化に関係して添加される光重合開始剤の添加量は,反応に十分な量であるとともに,過度であってもならないのであるから,反応硬化したインキ中に触媒反応していない光重合開始剤が充分残存していることはほとんど考えられない。 また,仮にこれが残存していたとしても,この光重合開始剤は,透明性を保ちながら紫外線から瓶の内容物を保護する紫外線吸収剤としての効果を目的として添加されたものではないから,前記(1)オ認定の本件考案にいう「紫外線吸収剤」には当たらない。 (4) 被告製品の透明部分について 原告は,被告製品には,透明部分にも紫外線吸収剤が含有されている旨主張する。 ア 前記(1)ウで認定したとおり,紫外線吸収剤とは,熱可塑性樹脂が最も影響を受ける300ないし400nmの紫外線を吸収して大部分を熱エネルギーに変換して放散するものである。 本来,紫外線吸収剤を添加したフイルムとこれを添加しないフイルムとの光線透過率には,顕著な違いが存在する。すなわち,紫外線吸収剤を添加した市販のPVCフイルムの場合は,420nm以上の可視光では80%程度の光線透過率であり,370nmから420nmにかけて光線透過率が減少し,370nm以下では光線透過率はほとんど0%となっている(乙39図1)。リンテック株式会社が製造する紫外線吸収機能のあるポリプロピレンフイルム OPP50C LS166G 8LKも同様である(乙40)。これに対し,紫外線吸収剤を添加していないPVCフイルムでは,300nmから400nmにかけて光線透過率は減少するものの50%以上の光線透過率を示しており,270nmあたりで光線透過率は0%となる(乙39図1)。 このように,紫外線吸収剤を添加した市販のPVCフイルムの370nm以下の紫外線透過率がほとんど0%となっていることからも,紫外線吸収剤を含有若しくは塗布しているといえるためには,400nm以下の紫外線領域における紫外線を充分吸収している必要があるといえる。 イ(ア) 愛知県産業技術研究所が行った被告製品の栓部の透明な部分についての可視紫外分光法による実験(甲36,37)によれば,被告製品は,波長400nm以上で光線透過率が約50%であり,波長300ないし400nmの領域での光線透過率の低下があり,約280nmで光線透過率がほぼ0%となる。また,愛知県産業技術研究所が行った被告製品の胴部の透明な部分についての可視紫外分光法による実験(甲38,39)によれば,被告製品は,波長330nm以上で光線透過率が約60ないし70%であり,波長330nm以下の領域で光線透過率の低下があり,約260ないし270nmで光線透過率がほぼ0%となる。名古屋市工業研究所が行った被告製品の無色部分についての紫外線可視吸収スペクトルの測定(甲48,49)によれば,波長400nm以上で光線透過率が85%以上であり,波長300ないし400nmの領域で光線透過率の低下があり,約250nmで光線透過率がほぼ0%となる。 以上の実験結果によれば,被告製品の透明部分においては,紫外線領域である波長300ないし400nmの領域において紫外線を十分吸収しているとはいえない。また,これらの実験は,光線透過率を測定したにすぎず,紫外線遮断の効果が紫外線の吸収によって得られていることを認めるに足りない。 (イ) 大日本インキ化学工業株式会社が行った光線透過率の測定実験(乙39)によれば,被告製品シュリンクPE70FLアオグラは,波長350nm以上の可視光では,80%程度のフラットな光線透過率を示し,300ないし350nmにかけて光線透過率が減少し,270nmあたりで0%となっている。そして,これは市販のシュリンクポリエチレン粘着シートとほぼ同じ光線透過率の減少傾向である。 (ウ) 以上の実験結果によれば,被告製品は,紫外線吸収剤を添加していない市販のフイルムと同様の光線透過率傾向を示しているということができ,紫外線吸収剤を添加したフイルムの光線透過率の傾向とは明らかに異なるものである。 ウ 被告製品の光線透過率が減少することは,被告製品が紫外線吸収剤を添加していることを直接示すものではないことに加え,前記イのとおり,被告製品は,紫外線透過率は減少しているとはいえ,400nm以下の紫外線領域では紫外線を透過しており,透過率がほとんど0%になるのは270nm以下にすぎない。 したがって,これでは紫外線吸収剤の特性を有しているとはいえない。 エ 原告が名古屋市工業研究所に依頼して行った紫外線可視吸収スペクトルの測定(甲42ないし44)によると,被告製品は,350ないし400nmで紫外線吸収スペクトルが約0.2であり,300ないし350nmにかけて紫外線吸収スペクトルが上昇し,波長300nmでは,約0.7に達する。しかし,上記アのとおり,紫外線吸収剤を含有若しくは塗布しているといえるためには,400nm以下の紫外線領域における紫外線を十分吸収している必要があるところ,被告製品は,波長350ないし400nmにおける紫外線吸収率は約0.2と少なく,波長300nmにおいても約0.7と紫外線吸収の効果は不十分であり,紫外線吸収率が1になるのは,波長290nm以下にすぎない。したがって,この実験結果によっても,被告製品は,300ないし400nmの紫外線を十分吸収しているとはいえず,紫外線吸収剤の特性を有しているとはいえない。 オ 被告製品には,容器への粘着剤が塗布されている(乙13)ことから,原告は,上記粘着剤に紫外線吸収剤が含有されているとも考えられると主張する。 粘着剤が塗布されている被告製品は,上記イで認定した光線透過率を示すが,粘着剤を除去した被告製品の光線透過率は,250ないし350nmにかけて透過率が減少し,230nmあたりで約0%となっており,粘着剤を塗布された被告製品と透過率に相違が見られる(乙39)。しかし,製造元の大日本インキ化学工業株式会社は,粘着剤層についても,紫外線吸収剤を紫外線吸収を目的として意図的に含有または塗布させていないとしている上(乙13),上記イ及びエのとおり,粘着剤を塗布した被告製品は,紫外線を充分吸収しているとはいえない。 カ 以上のとおり,被告製品の透明部分のフイルムも紫外線吸収剤を含有若しくは塗布しているということはできない。 (5) したがって,被告製品は,本件考案の構成要件C「紫外線吸収剤」を充足しない。 2 争点(2)(収縮率)について (1) 構成要件Dの意義 ア 原告は,構成要件Dにおける技術的思想の核心的部分は,縦の収縮率と横の伸縮率が大きく異なるという異方性にあるから,「100℃」「45%以上」「10%以下」という具体的数値を充たさなくても,縦横の収縮率の比が45/10以上であれば,被告製品は実質的に構成要件Dを充足する旨主張する(前記第3の2〔原告の主張〕(1))。 イ しかしながら,登録実用新案の技術的範囲は,願書に添附した明細書の実用新案登録請求の範囲に基づいて定めなければならないことは,実用新案法26条の準用する特許法70条1項の定めるところである。原告の主張は,本件実用新案登録請求の範囲中に具体的に明記されている数値を無視して,請求の範囲中に記載されていない縦と横の収縮率の比が構成要件Dの内容であると解釈するものであって,法令の定めるところに違反することが明らかである。しかも,測定温度によって収縮率や伸縮率が大きく異なることにも照らせば(甲7,乙3,9の2,16),実用新案登録請求の範囲に記載された測定温度と異なる温度による場合には,上記数値限定が意味をなさなくなってしまうから,「100℃」という温度や「45%以上」「10%以下」という数値を無視した解釈をすることはできない。 ウ また,本件明細書には熱収縮率の測定温度について100℃以外の温度の記載がない上,原告は,審判請求理由補充書(乙12)及び意見書(乙28)において,「本考案では,45%以上と大きな熱収縮率に特定してあるため,皺が感圧接着剤で既に接着固定されていても微細な皺を延ばすことができます。」(乙12),「一方,ラベルフイルムが第4図の状態から第3図のように,薬瓶の細口部分に収縮して,かつ瓶の底に回り込み,しっかりと瓶を包装するようにするためにも,45%以上の収縮率が必要となります。また,45%以上の収縮力であれば,感圧接着剤の接着量に対抗して皺を除去できる収縮力があること並びに,細口部分及び底部分が第3図の形状に包装できることを,実際に実施して確認しています。」(乙28),「そして,横方向の熱収縮率は10%以下にすれば,横方向への熱収縮は感圧接着剤の接着力で抑えられ,表示の変形はまったくないことを見いだした点に考案力が十分に存在するものと思考します。」(乙12)などと主張して,細口瓶に適用されるが熱収縮率の具体的値の記載のない引用文献1(乙21)に記載されるフイルムとの差異を強調している。 エ したがって,被告製品が構成要件Dを充足するためには,構成要件Dに記載されている具体的な数値をすべて充たす必要がある。 (2) 縦方向の収縮率及び横方向の伸縮率の測定方法について 縦方向の収縮率及び横方向の伸縮率について,本件実用新案登録請求の範囲中には,測定温度については「100℃」という明確な記載があるものの,加熱時間(浸漬時間)その他具体的な測定方法についての記載はない。また,本件明細書中にも,これらの測定方法について,明示的に示唆する記載はない。以下,測定方法について,検討する。 ア 測定温度について まず,測定温度については,本件実用新案登録請求の範囲中に,「100℃」という明確な記載がある以上,被告製品の収縮率は,100℃で測定された実験値のみを採用すべきであることは明らかである。したがって,原告が主張するような,108℃,110℃,120℃といった測定温度での実験値や,そこから推測して算出した収縮率の値などは,いずれも採用することができない。 イ 加熱時間について 次に,加熱時間については,本件明細書中には,「この縦方向の熱収縮率が45%未満の場合は,細口栓の部分の包装が密着しなかったり,皺ができたりする。また,横方向の熱収縮率が10%以上になるとラベルの表示が収縮によって変形する可能性がある。」(3欄40ないし43行)との記載があり,本件考案で指定する熱収縮率が達成できなかった場合の熱収縮工程における具体的な短所を指摘していることから,本件考案における熱収縮率は,包装時の熱収縮工程において達成すべき収縮率を特定していると解される。 また,本件明細書の実施例には,「100℃のシュリンクトンネルの中に入れて,熱収縮フイルム1の上方の瓶から遊離している部分を熱収縮させて瓶に密着させる。シュリンクトンネル内では,赤外線又は熱風によって1~2分間熱収縮温度で加熱する。」(5欄23ないし30行)との記載がある。熱収縮率は加熱時間が長くなるほど大きくなるから(甲14,15,乙16),2分を超える時間を基準として収縮率を規定したとすると,本件考案において想定された熱収縮加工時間である1ないし2分間に,縦方向における収縮率45%を達成することができなくなり,包装が密着しなかったり,皺ができたりして,結局,本件考案の指摘する課題を解決できなくなる。そうすると,加熱時間は,2分を超えることはないものと解される。 したがって,原告が主張する10分又は20分といった長時間の加熱時間は採用できない。また,本件考案におけるラベルの収縮率は,長時間浸漬した結果,文字どおり収縮が完了した状態での収縮率(最大収縮率)であると解することもできない。 ウ 測定方法について 測定方法について,本件明細書の実施例には,「100℃のシュリンクトンネルの中に入れて,熱収縮フイルム1の上方の瓶から遊離している部分を熱収縮させて瓶に密着させる。シュリンクトンネル内では,赤外線又は熱風によって1~2分間熱収縮温度で加熱する。」(5欄23ないし30行)との記載があり,この熱収縮方法は,赤外線又は熱風によるものである。 他方,JIS規格Z1709-1995(甲8,乙14)では,恒温浴槽内にエチレングリコール又はグリセリンなどの熱媒液を充たし,ステンレス製金網などで熱媒液が自由に環流でき,かつ試験片が浮き上がらないように軽く抑える構造のフイルム支持具内に試料を置き,所定の温度を保った熱媒液中に手早く浸漬し,所定時間加熱し,自由に収縮させた後取り出して,別に用意した常温の浴液に浸し,約5秒間冷却した後取り出し,平らに静置して30分以内に縦,横の寸法を測る,という熱媒液による方法が記載されていること,一般に物の製造に用いられる材料の物性を測定する場合には,その測定に必要な大きさの試験片を用いて,実験室レベルでの実験を行う場合がほとんどであることからすれば,本件考案に規定される熱収縮率の測定方法は,赤外線又は熱風による加熱には限られないと解される。もっとも,上記JIS規格は,本件出願日後である平成7年の規格であるから,この熱媒液による方法が標準的な測定方法であると限定することもできない。 したがって,赤外線又は熱風による方法も,熱媒液による方法も,一応採用することができる。 (3) 被告製品の収縮率及び伸縮率 ア 東京都立産業技術研究所作成の成績書(乙16)によると,被告製品の100℃における縦方向の収縮率は,20%程度であり,2分間加熱しても27.9%であることが認められるから,被告製品は構成要件Dを充足しない。 すなわち,被告は,東京都立産業技術研究所に,被告製品であるPE70タックシュリンクラベルのフロバール点眼液ラベル,メインター点眼液ラベル,チモロール点眼液ラベル(乙15)を試料とする熱収縮実験を依頼した。実験は,JIS規格を参考に行われ,試料を剥離紙から剥がし,約100×100㎜の2枚の金網間に配置して,これを100℃,105℃,110℃の温度にそれぞれ保ったシリコンオイルバス中に,20秒又は30秒間浸漬した。その後,直ちに常温の浴液に浸し,30分以内に試料の横方向の二辺の長さを1㎜まで測定して収縮率を求めた。試料1に関しては,100℃の浸漬温度において,60秒,300秒,1800秒,3600秒間浸漬した実験も行った。2枚の金網の間には,試料より厚い厚さ約3ないし4㎜のスペーサーを挟み込んでおり,試料が金網に押さえられることなく自由に動けるようにしてある(乙31の2)。 その結果,100℃の浸漬温度において20秒間浸漬した各試料の収縮率は,それぞれ17.2%,14.8%,17.4%であった。100℃で30秒間浸漬した各試料の収縮率は,それぞれ19.5%,19.0%,19.0%であった。また,試料1については,100℃の浸漬温度において,浸漬時間60秒間で23.4%,300秒間で27.9%,1800秒間で27.3%,3600秒間で31.3%であった(乙16)。 したがって,上記実験は,前記(2)で認定した測定条件を充たし,かつ,東京都立産業技術研究所が測定値を左右するような作為的な実験を行ったとも認められないから,上記実験結果は採用し得るものである。 イ この点につき,原告は,測定試料は2枚の金網に挟んで測定されているため,① 金網との物理的接触,② 接着剤による金網との粘着,③ 金網の比熱によるシリコンオイルの温度低下の各要因が収縮率にマイナスに作用していると主張する。しかしながら,上記のとおり,① 金網の間には,スペーサーを挟み込んでおり,試料の収縮を妨げないようにしてあるし,② シリコンオイルの中では,接着剤は粘着しないので収縮率に特にマイナスに作用するとは考えられない。③ 金網による温度低下の点も,恒温油槽中で温度管理をしている状態において,金網の外の温度と約3㎜ないし4㎜の金網の中の空間とで測定結果に影響を与えるような温度差が生じているとは考えられない。 (4) 原告提出の実験結果について これに対し,原告は,法令に反するクレーム解釈を前提として,原告提出の実験結果によれば,被告製品は構成要件Dを充足する旨主張し,訴訟指揮に従うことなく次々に実験を行って,以下のとおり証拠を提出した。 ア リンテック株式会社作成の報告書(甲7) 甲7は,リンテック株式会社がLM151Eという試料についての一般物性を測定したものである。この試料が被告製品であるか否かは明らかでないが,この点はさておいても,実験結果は,100℃,10秒間の縦方向の収縮率が20%であるというもので,構成要件Dの数値を充足しない。 イ 原告作成の収縮実験結果報告書(甲15,16) 甲15は,原告が市場から入手したメインター点眼液の栓上部のラベルを容器から剥がして試料とし,食塩水溶液をバットに入れて加熱浴槽とし,水溶液温度をほぼ100℃に維持するように加熱して15分間隔で収縮率を計測したところ,90分及び105分加熱後の計測値はいずれも38%であったというものである。本件考案実施時の熱収縮工程においては,未使用の状態のフイルム(乙15)を使用することが前提とされていることは明らかであるから,熱収縮実験に際しても,未使用の状態のフイルムを試料とすべきであるところ,原告の実験は,一旦加熱収縮が施されたフイルムを試料としている点において実験が不正確となっている。その上,実験方法において,上記(2)で示した測定時間を充たしておらず,かつ,その実験結果は,45%以上という本件実用新案登録請求の範囲の数値を充たしていないから,これにより被告製品が構成要件Dを充足するとはいえない。 甲16は,甲15と同様にして,105℃で10分間加熱した場合の収縮率の計測値は43%,108℃で10分間加熱した場合は47%を示したというものである。しかし,甲15と同様の問題がある上,本件実用新案登録請求の範囲に記載された測定温度である100℃という条件を充たさないことが明らかであるから,この実験結果は採用できない。 ウ リンテック株式会社作成の報告書(甲17)及び原告補佐人作成の宣誓供述書(甲18) 甲17は,リンテック株式会社が,点眼液瓶に貼付されているシュリンクラベルを剥がして試料とし,高濃度の食塩水を沸騰させて約105℃前後にしたものが入ったウォーターバスの中に,グリセリンの入ったビーカーを入れ,100℃の温度領域に調整されたグリセリン浴に,上記ラベルの栓部と胴部の測定用試料を10分間浸漬したときの収縮率を測定したところ,測定試料は,栓部及び胴部ともに,その収縮率が縦方向で47%,横方向で0%であったというものである。 また,甲18は,東京工業大学資源化学研究所a助教授に試験の立会を依頼し,原告補佐人が実験を行い,市場より入手したメインター点眼液瓶に装着されているラベル製品の胴部分を剥がして試料とし,300?コニカルビーカーにグリセリンを入れ,煮沸している塩水温浴中(食塩の飽和水溶液:測定温度107℃)にコニカルビーカーを保温し,ガラス棒にて撹拌しながらグリセリン温度を100℃に保持し(アルコール棒温度計により確認),前記試料をグリセリン中に浸漬し,10分後の収縮率を測定したところ,縦の収縮率が43.1%,横の伸縮率が0%であったというものである。 甲17が被告製品について行われたものか否かについては,必ずしも明らかではないが,この点はさておいても,甲17及び甲18の実験は,いずれも点眼液の瓶から被告製品を分離して試料としており,一旦加熱収縮が施されたフイルムを試料としている点において実験が不正確となっている上,10分という前記(2)イで認定した適切な加熱時間を大幅に超える加熱時間を採用しており,熱収縮率が本来の測定値より高くなっていると考えられる。ことに,甲18は,JIS規格に記載されているグリセリンにより測定するとしながら,JIS規格では120℃で浸漬時間20秒とされているから,100℃であれば浸漬時間を長くしなければ意味がないとして,浸漬時間をJIS規格を大幅に上回る10分としているところ(甲22),120℃の場合より加熱時間を多少長くする必要があるとしても,120℃の場合の加熱時間20秒の30倍もの時間加熱することが相当でないことは,前記(2)イに述べたことからも,明らかである。したがって,これらの実験結果は採用できない。 エ 愛知県産業技術研究所作成の成績書(甲20)及び大阪府立産業技術総合研究所作成の報告書(甲21) (ア) 甲20は,愛知県産業技術研究所が,メインター点眼液瓶に装着されている被告製品から,ラベルの胴部と栓部を剥がし,それぞれについてエチレングリコールの100℃恒温浴槽による収縮実験を行ったものである。試験装置は,染色試験機ミニカラー(テクサム技研 MC12ELB)で,エチレングリコールの温度は100℃に保持する設定であるが,実測値として101℃とされた。試料をメッシュ容器に入れ,試験機のエチレングリコール溶液漕に10分間浸漬後,室温で冷却して長さを測定し,収縮率を測定したところ,胴部で横(フイルムの縦方向)の収縮率が46%,縦(フイルムの横方向)の収縮率が-3%の試験結果が得られ,栓部は同様に44%,-1%であった。 また,甲21は,大阪府立産業技術総合研究所が,JIS規格に基づき,グリセリン約300㏄を500㏄のビーカーに入れ,熱伝対と温度制御装置,撹拌スターラーにより温度制御した油浴中にてあらかじめ100℃に加熱し,グリセリン中に原告から提出された試料を挿入し,20分間加熱した後,収縮率を測定したところ,46.4%であったというものである。 甲21が被告製品について行われたものか否かについては,必ずしも明らかではない。また,甲20の実験も,点眼液の瓶から被告製品を分離して試料としており,一旦加熱収縮が施されたフイルムを試料としている点において実験が不正確となっている。さらに,いずれの実験も,10分ないし20分という前記(2)イで認定した適切な加熱時間を大幅に超える加熱時間を採用しており,熱収縮率が本来の測定値より高くなっていると考えられる。 したがって,上記(ア)における甲20及び甲21の実験結果は採用できない。 (イ) なお,大日本インキ化学工業株式会社作成のシュリンクPE粘着ラベルの熱収縮率測定結果(乙41)によれば,次の事実が認められる。 乙41は,大日本インキ化学工業株式会社が,愛知県産業技術研究所の測定方法(甲20)に準じた条件で,被告製品であるシュリンクPE70FLアオグラを使用したメインター点眼液ラベル及びフロバール点眼液ラベルについて,熱収縮性の実験を行った結果である。恒温浴槽にはオイルバスOHB-1000S(東京理化器械社製),熱媒体にはグリセリンを使用し,101℃に設定して測温抵抗器で測定したところ,101.3℃であった。試験方法は,① 上記オイルバスにグリセリンを満たし,マグネチックスターラーにて撹拌しながら101℃の設定で加熱する。② 金網かごに入れた試料(栓部と胴部を切り離したもの)を10分間浸漬する。③ 取り出した後,室温で冷却し,ノギスで寸法変化を測定するものである。その平均収縮率の結果は,メインター点眼液ラベルでは,栓部,胴部ともに30%,フロバール点眼液ラベルでは,栓部が32%,胴部が31%であった。 (ウ) さらに,愛知県産業技術研究所作成の成績書(乙43)によれば,次の事実が認められる。 乙43は,愛知県産業技術研究所が,被告製品であるメインター点眼液ラベル及びフロバール点眼液ラベルについて,収縮率の実験をした結果である。 温度管理は,試験装置である染色試験機ミニカラー(テクサム技研 MC12ELB)の制御板の設定及び温度制御装置により自動制御され,被告が持ち込んだ検定済みハンディタイプデジタル温度計(DP-500R 理化工業。乙44ないし46)により,油槽内の熱媒であるエチレングリコールの温度が平均101℃であることを確認した。試料をメッシュ容器(金属製の同心状の2重円筒の中筒。乙42)に入れ,試験機のエチレングリコール溶液漕に10分間浸漬後引き上げ,室温で冷却して長さを測定し,収縮率を3回測定した。その結果,メインター点眼液ラベルの収縮率は,栓部が29%,胴部が28%,フロバール点眼液ラベルの収縮率は,栓部,胴部ともに28%であった。 (エ) 上記乙41及び43の実験結果は,愛知県産業技術研究所作成の成績書(甲20)の実験結果と異なっているが,上記実験で用いられたデジタル温度計が試験装置の温度制御装置の設定温度より0.4ないし1℃高い温度を示し,水銀温度計ともほぼ一致した温度を示すのに対し,甲20で用いられたアルコール温度計は,設定温度より3ないし4℃低い温度を示し,水銀温度計ともその示す温度差が大きいこと(乙42)からすると,他の実験条件が同じである場合には,乙41及び43の実験の方がより信憑性が高いといえるものである。 したがって,仮に原告の甲20における10分間という加熱時間を採用したとしても,被告製品の100℃における収縮率は45%未満であると認められるものである。 オ 原告作成の収縮実験結果(甲35の1ないし7) (ア) 甲35の1ないし7は,原告が,市中から入手したメインター点眼液瓶に装着されている被告製品のラベル胴部を剥がし,円筒状の疑似容器に対し,その上部から突き出るように,被告製品を円筒状に巻き付け,表面温度感熱示温ラベルと称される温度計(「THERMAX」4レベルマイクロラベル レンジ「M/L4」。甲34の1ないし3)を被告製品の上部表面に予め貼り,ハンドライスターを使用して簡易収縮装置から熱風をその突き出たラベル上部付近に当て,被告製品の表面温度を示温ラベルで測定しつつ,上記突き出たラベル部分を収縮させ,その収縮率を測定したところ,示温ラベルが92℃以上100℃未満(±1℃誤差を考慮)でそれぞれ3つの試料につき,いずれも縦の熱収縮率は48%以上であったというものである。 (イ) 他方,大日本インキ化学工業株式会社作成の感熱示温ラベルによるシュリンクPE粘着ラベルの収縮温度調査結果(乙47)によれば,次の事実が認められる。 乙47は,大日本インキ化学工業株式会社が,熱風装置に白光株式会社製ヒートガン №883-13(熱風出口実測温度:約200℃)を使用し,感熱示温ラベルに「THERMAX」4レベルマイクロラベル レンジ「M/L4」を使用して,甲35の1ないし7と同様の実験をし,メインター点眼液用の容器に約18㎜高さを容器上部に出して,被告製品シュリンクPE70FLアオグラを使用したメインター点眼液ラベルの胴部を貼付し,100rpmの回転を与えながら所定時間加熱したところ,感熱示温ラベルの表示が99℃まで黒色化した場合(99℃以上104℃未満)でも,収縮率は31%であったというものである。 (ウ) 甲35の1ないし7の実験も,乙47の実験も,被告製品が装着された瓶から被告製品を分離して試料としており,一旦加熱収縮が施されたフイルムを試料としている点で実験が不正確となっている。また,いずれも収縮率の数値に影響を与えると解される加熱時間の記載がない。 また,甲35の1ないし7の実験方法は,ラベルの収縮が規制されるような疑似容器にラベルを貼り付け,ハンドライスターという,ラベル全体を均一に加熱・収縮し得ない加熱方法を採用して行われたものである。さらに,収縮立ち上がり部は,精緻な円形をしているものでないにもかかわらず(甲35の4),収縮立ち上がり部外径を疑似容器の直径で除するという計算式によって収縮率を算出しており,正確な熱収縮率の算出方法であるとは認められない。 したがって,熱風による実験結果は,いずれも採用できない。 カ 以上のとおり,原告の提出した実験結果は,いずれも,試料に問題があったり,測定条件を外れた10分以上という長時間加熱したこと等によって,収縮率が高くなったりしたもので,その実験結果をもって構成要件Dを充足すると認めるに足りない。 (4) よって,被告製品は,構成要件Dを充足しない。 3 争点(3)(均等論)について 本件実用新案登録請求の範囲に記載された構成中に被告製品と異なる部分が存する場合であっても,① 上記部分が本件考案の本質的部分ではなく,② 上記部分を対象製品等におけるものと置き換えても,本件考案の目的を達することができ,同一の作用効果を奏するものであって,③ 上記のように置き換えることに,本件考案の属する技術の分野における通常の知識を有する当業者が,被告製品の製造等の時点において容易に想到することができたものであり,④ 被告製品が,本件考案の出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから上記出願時に容易に推考できたものではなく,かつ,⑤ 被告製品が本件考案の出願手続において実用新案登録請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは,被告製品は,本件実用新案登録請求の範囲に記載された構成と均等なものとして,本件考案の技術的範囲に属するものと解するのが相当である(最高裁平成6年(オ)第1083号同10年2月24日第三小法廷判決・民集52巻1号113頁参照)。 (1) 本件明細書には,構成要件Dに関連して,以下の記載がある(甲2)。 ア 「本考案者らは,細口瓶用の包装のためには,熱収縮率の大きいフイルムを使用する必要があり,しかも,その収縮方法に異方性を持たせ,縦方向を45%以上として,横方向を10%以下とすれば,前記のような問題点を解決できることを見い出し,本考案を完成した。」(3欄11ないし15行) イ 「本考案に使用する熱収縮フイルムは,ラベルとして使用した場合の縦方向の熱収縮率は100℃において45%以上,好ましくは55%以上であり,横方向の熱伸縮率は10%以下,好ましくは5%以下,さらに好ましくは2%以下である。この縦方向の熱収縮率が45%未満の場合は,細口栓の部分が密着しなかったり,皺ができたりする。また,横方向の熱収縮率が10%以上になるとラベルの表示が収縮によって変形する可能性がある。」(3欄35ないし43行) ウ 「本考案ラベルは,細口瓶の胴体部分に殆ど密着させて巻き付けて使用する。そのため,胴部分に関しては,ラベルの皺をとることができる程度の熱収縮率があれば十分である。しかし,細口瓶の栓部分を密着包装するためには,45%以上の熱収縮率が必要となる。」(4欄9ないし14行) エ 「本実施例の熱収縮フイルムの代わりに縦方向の熱収縮率40%のポリ塩化ビニルフイルムを使用して同様に熱収縮により包装したが,栓部分の密着がなく,フイルムがその部分から浮いて体裁よく封印することができなかった。」(6欄9ないし13行) (2) このように,本件明細書において,熱収縮フイルムの100℃における縦方向の熱収縮率を45%以上,横方向の伸縮率を10%以下とすることが,細口瓶の栓部分に対しても密着包装ができるという技術的課題を解決するための手段であることが記載されている。また,熱収縮率が45%未満の場合には,上記技術的課題を適切に解決できないこと,実際に熱収縮率40%のフイルムを使用した場合は,体裁良く封印できなかったことが記載されている。審判請求理由補充書及び意見書においても同様であることは,前記2(1)認定のとおりである。 したがって,これらの記載からすると,原告は,縦方向の100℃における熱収縮率が45%未満のものについては,意識的に除外していたと認められる。 また,100℃における熱収縮率が45%未満の場合には技術的課題を解決できないのであるから,この数値限定には臨界的意義があり,「縦方向の100℃における収縮率が45%以上」という要件は,本件考案の本質的部分であると解される。 (3) 以上のとおり,本件においては,均等の要件のうち,前記①の要件(本質的部分ではないこと)及び前記⑤の要件(意識的に除外されたものでないこと)を充たさないから,被告製品が本件考案と均等であるとはいえない。 4 争点(4)(細口瓶)について (1) 構成要件A及びHの「細口瓶」の技術的意義 ア 本件明細書には,細口瓶について,次のような記載がある(甲2)。 (ア) 「本考案者の一部は,熱収縮フイルムの裏に接着剤を塗布して,表示が脱落しないラベルを開発したが,これより大きな曲面をもつ細口瓶に使用すれば,瓶の栓・肩の部分(以下,栓部分と称す)の密着性が不十分であり,栓部分のフイルムや印刷箇所に皺ができて,包装が運送中に破れやすい上に体裁が悪い。」(2欄14行ないし3欄5行) (イ) 「本考案者らは,細口瓶用の包装のためには,熱収縮率の大きいフイルムを使用する必要があり,しかも,その収縮方法に異方性を持たせ,縦方向を45%以上として,横方向を10%以下とすれば,前記のような問題点を解決できることを見い出し,本考案を完成した。」(3欄11ないし15行) (ウ) 「この縦方向の熱収縮率が45%未満の場合は,細口栓の部分が密着しなかったり,皺ができたりする。」(3欄40ないし41行) (エ) 「本考案ラベルは,細口瓶の胴体部分に殆ど密着させて巻き付けて使用する。そのため,胴部分に関しては,ラベルの皺をとることができる程度の熱収縮率があれば十分である。しかし,細口瓶の栓部分を密着包装するためには,45%以上の熱収縮率が必要となる。」(4欄9ないし14行) (オ) 「本実施例の熱収縮フイルムの代わりに縦方向の熱収縮率40%のポリ塩化ビニルフイルムを使用して同様に熱収縮により包装したが,栓部分の密着がなく,フイルムがその部分から浮いて体裁よく封印することができなかった。」(6欄9ないし13行) イ また,審判請求理由補充書(乙12)には,次のような記載がある。 (ア) 「なお,一般に細口瓶とは,栓の外径が胴部の外径の70%以下のものを言います(日本薬局方等)。」(4頁7ないし8行) (イ) 「引用文献1のラベルの適用対象物は,細口瓶ではありません。本願考案は細口瓶の形状,すなわち,細口部分が胴部分の70%以下の直径という状態で発生する特別の技術的問題の解決であります。」(10頁3ないし5行) (ウ) 「引用文献1の熱収縮フイルムは,縦方向の熱収縮率45%以上及び横方向の熱収縮率に異方性がある特殊な熱収縮フイルムではありません。本願考案は,細口瓶で発生する特殊の課題をこの熱収縮率の異方性によって解決したものであります。」(10頁7ないし10行) ウ 上記ア(ア)の記載からすると,細口瓶とは,栓部と胴部の径に顕著な差がある結果,栓をした状態での瓶に肩部が形成されるような瓶を意味しており,上記ア(イ)(ウ),イ(ア)などの記載からすれば,本件考案は,このような栓部と胴部の径に顕著な差がある特定の形状の瓶に対して,その径の細い部分に対しても皺のない包装を可能とするために,適用する熱収縮フイルムの縦横の熱収縮率を特定の値の範囲になるようにしたものである。 したがって,構成要件A及びHにいう「細口瓶」とは,本件明細書第3図に記載されているように,少なくとも栓部と胴部との径に顕著な差がある結果,栓をした状態での瓶に肩部が認められるような瓶を意味するものというべきである。 (2) 被告製品における細口瓶 しかしながら,被告製品が実際に使用されている瓶は,栓部分と胴部分の径がいずれも等しいかあるいはほとんど差がなく,栓をした状態での瓶に肩部が認められない(甲9ないし13,乙2の2,乙3)。したがって,被告製品は,「細口瓶」には使用されていないので,被告製品が使用されている瓶が構成要件A及びHを充足するものとはいえない。 また,前記2で認定したとおり,被告製品は100℃における縦方向の熱収縮率が45%以上とはいい得ないから,上記(1)ア(ウ)に記載されているとおり,細口瓶に使用した場合は,本件考案が想定する技術的問題の解決ができない。したがって,被告製品は,本件考案の実施にのみ使用するものであるとはいえない。 (3) 原告の主張について 原告は,「細口瓶」とは,注出口の内径(口内径)が胴部分の直径の70%以下であることを典型事例として想定していると主張するが,本件考案の包装ラベルは,構成要件Eにあるように,「瓶の栓部分に対応する部分」が必要であり,当該包装は,栓をした細口瓶に対して施されるものと解されるから,注出口の内径は本件考案とは無関係である。 また,原告は,栓(蓋)の上部が円錐状になっていて栓外径が変化している場合も含むと主張しており,被告製品が使用される瓶の中には,その栓の先端の一部分が他の部分に比して小径となっているものも存在する(甲9ないし11)。 しかし,いずれも栓部と胴部の境界部付近においては,径に差がなく,栓をした状態での瓶に肩部は形成されていない。また,他の部分に比して小径となっている先端部分には,被告製品は包装されておらず,本件考案が課題の解決策として示す縦方向の熱収縮率が45%以上であることは全く必要のない状態である。したがって,これらの瓶は,「細口瓶」に該当しない。 5 結論 よって,その余の点につき判断するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がないから,棄却することとして,主文のとおり判決する。 |
|
| 追加 | |
|
物件目録1(1)大日本インキ化学工業株式会社が「シュリンクPE70FL-MPET」の製品名で被告に納入している粘着剤付熱収縮フイルムに,細口瓶の胴部に相当する位置に印刷を施し,かつ細口瓶の胴部と栓部との間にミシン目を設けた「タックシュリンクラベル」と称している包装ラベル。 (2)上記(1)の包装ラベルの販売の申出のために,被告が顧客に配布している「タックシュリンクラベルのご提案」と称するパンフレット。 物件目録2大日本インキ化学工業株式会社が「シュリンクPE70FL-MPET」の製品名で被告に納入している粘着剤付熱収縮フイルムに,被告が印刷を施し,「タックシュリンクラベル」と称している包装ラベル。 〔構成〕上記フイルムの断面は,上部から次の①ないし④の順に構成されている。 ①アンカーコート層(印刷面)②熱収縮性フイルム(包装フイルム基材)③粘着剤層(容器への粘着剤)④グラシン系剥離紙(表面シリコーン塗布)〔形状〕別紙のとおりの形状を基礎として,胴部に薬品名等の印刷を施して使用される。 縦47㎜,横64㎜。 容器に接着する際,胴部に相当する部分と栓部に相当する部分の間にミシン目が設けられている。栓部には,さらに縦に2本のミシン目が設けられている。 胴部は,UV白インキによって,白色に塗られており,その上に,「チモロール点眼液」「コバラム」「フルオメソロン」「メインター点眼液」といった薬品名等が印刷されている。 栓部は,UV白インキによって,白色に塗られたものと透明なままのものと2種類存在する。 (別紙)タックシュリンクラベル |
| 裁判長裁判官 | 高部眞規子 |
|---|---|
| 裁判官 | 東海林保 |
| 裁判官 | 瀬戸さやか |